心療内科・精神科経営シリーズ第1回|2026年度診療報酬改定から考える“経営の3つの視点”
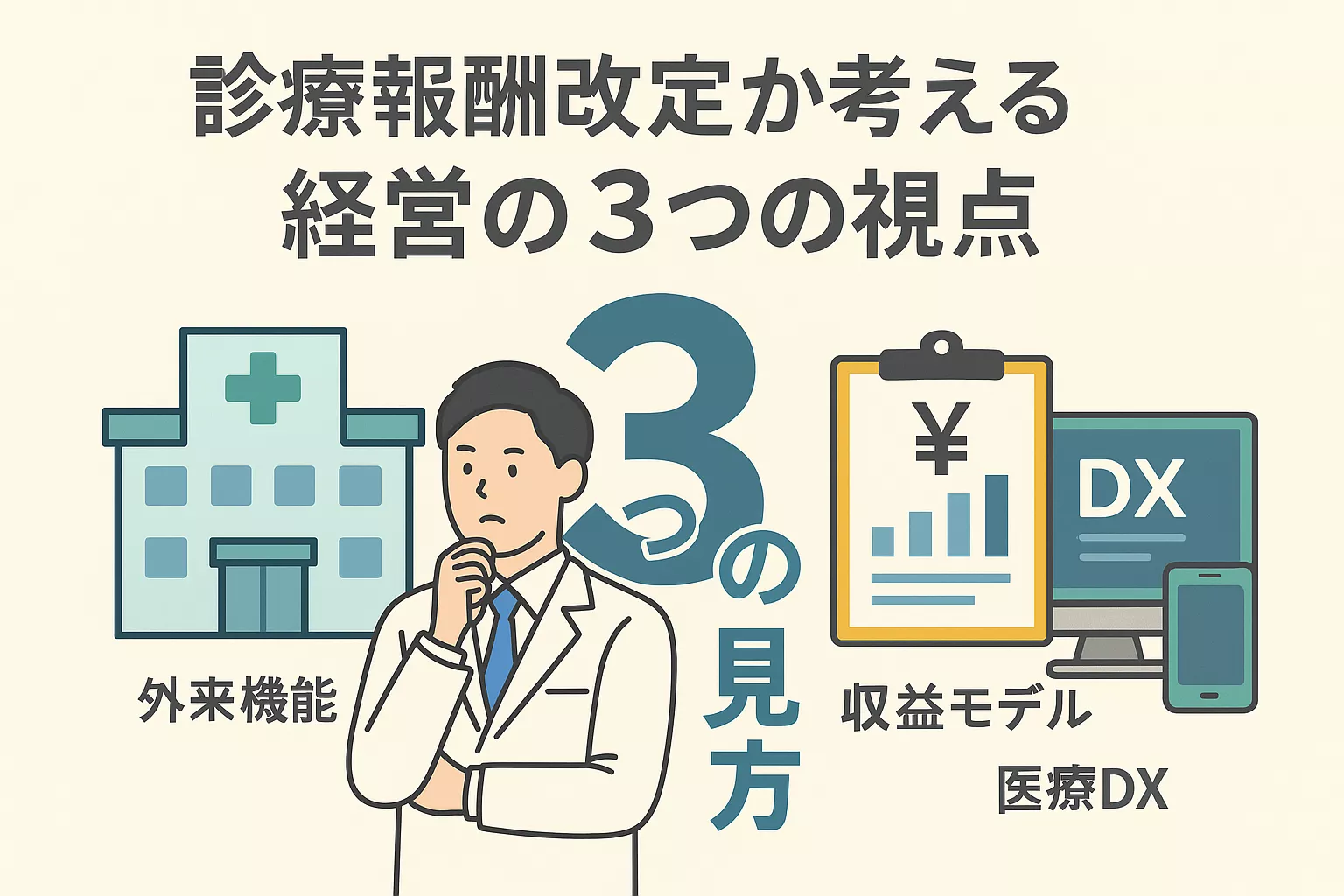
本記事は「診療科目別経営戦略/心療内科・精神科経営シリーズ」に属します。
2026年度の診療報酬改定の流れを踏まえ、心療内科・精神科クリニックの外来機能・収益モデル・医療DXを整理します。
この記事で整理できること
- 外来機能(初診・再診の配分/地域での役割)を、制度の流れとセットで言語化する
- 収益モデルを「売上を伸ばす」ではなく、負担を分散し継続できる形として捉え直す
- 医療DXを「効率化」ではなく、“人の時間を取り戻す道具”として導入設計する
目的は「正解探し」ではなく、院長ご自身の診療理念に沿って“選び取れる状態”をつくることです。
✅ 読み終えたら、まずは「自院は、どの患者層を、どこまで支えるのか」を1文で書いてみてください。
もし書けない場合は、迷いの原因は知識不足ではなく、前提(役割・範囲・時間配分)がまだ言語化されていない可能性が高いです。
2026年度の診療報酬改定では、心療内科・精神科クリニックにとっても“経営の前提”が揺れる可能性があります。
外来機能の整理、継続的な支援の評価、地域連携の強化、医療DXなど――現場の運用に直結する論点が多く含まれるためです。
ただし、改定は「制度に振り回される出来事」ではありません。
「これからの診療を、どう支え続けるか」を再確認し、外来・人員・時間配分を整えるきっかけにもなります。
本記事では、心療内科・精神科の院長先生が経営の舵取りをするうえで、まず押さえておきたい3つの視点を、できるだけシンプルに整理します。
心療内科・精神科は、他科と比べて改定の影響が“一気に診療の形を変える”というより、継続診療や地域連携のあり方を、少しずつ整えていく方向で現れやすい領域です。
影響は緩やかでも、外来の設計次第で差が出る――そのタイプの変化だと捉えるのが自然だと思います。
その背景には、心療内科・精神科がもともと、診察(診療)・関係性・連携の質そのものが価値になりやすい診療領域であることがあります。
一方で、長期処方やリフィルといった流れとも無縁ではなく、「どこまでを診察で支え、どこからを連携で支えるか」、そして診療時間(面談時間)と運用のバランスは、経営にも確実に影響します。
ここでは制度の“正解”を当てにいくのではなく、院長の診療理念に沿って、続けられる外来の形を言語化するところから整理していきます。
1. 外来機能をどう位置づけるか
※2026改定では、かかりつけ機能/地域連携/紹介・逆紹介の整理など、「地域の中での役割」が改めて問われやすい流れです。
診療報酬の議論では、地域医療の中で「かかりつけ機能」と「専門機能」をどう整理するかが、大きなテーマになります。
心療内科・精神科では、長期フォローが必要な患者さんと、初診で不安を抱えて来院される方の両方を支える必要があり、外来設計が複雑になりやすい領域です。
たとえば、初診枠を曜日・時間帯で明確に区切る、紹介(内科・婦人科・産業医等)の受け入れ条件を整理する、再診の通院頻度を院内基準として揃える――。
こうした運用は「縛り」ではなく、自院が担う役割を明文化するための設計です。
ここで詰まりやすいのは、制度の理解ではなく、「どこまで支えるか」の線引きです。
まずは院長として「誰を、どの状態で、どこまで支えるのか」を言語化してみてください。
書こうとして言葉が止まる場合、迷いの“芯”は、外来の枠ではなく役割の定義にあることが多いです。
2. 収益モデルを多角的にとらえる
※2026改定の議論は、単価そのもの以上に、継続支援の評価/多職種連携/患者のアウトカムといった「提供価値の見える化」へ寄りやすい点がポイントです。
心療内科・精神科クリニックは、再診中心になりやすく、収入の上限が見えやすい構造があります。
ここで大事なのは、単に「収益を増やす」よりも、支援を続けられる形に“負担を分散する”という発想です。
たとえば、予約料の導入はキャンセル・無断欠席のリスクを下げ、医師・スタッフの時間を守る仕組みになります。
導入の際は、患者さんへの丁寧な説明や、法的な整理(運用ルールの設計)を踏まえて進めるのが前提です。
※予約料は地域性・患者層・説明設計によって適否が分かれるため、「自院の役割と外来設計」とセットで検討するのが安全です。
👉 導入手順の詳細は 心療内科クリニックにおける予約料導入の流れ で解説しています。
また、臨床心理士・公認心理師の活用は、医師一人では支えきれない領域を補完し、心理検査・カウンセリング等を通じて診療の幅を広げます。
ここでのポイントは、数字の拡大だけではなく、院長・スタッフが疲弊しない“余白”をつくること。
経営の安定とは、拡大よりもまず「続けられる状態」をつくることでもあります。
収益モデルを考えるときに迷いやすいのは、「何を増やすか」ではなく「何を守るか」です。
まずは、守りたいもの(診療の質/面談時間/スタッフの負担/待ち時間)を1つ決めてください。
そこが決まると、予約料や心理職の活用は「手段」として位置づけやすくなります。
3. 医療DXをどう活用するか
※2026改定は、医療DX(オンライン資格確認・電子処方箋など)を前提に、業務の標準化/情報連携/負担軽減が求められやすい流れです。
AI問診、予約システム、電子カルテ、電子処方箋、オンライン資格確認――。DXは運用を軽くする強力な手段です。
ただし心療内科・精神科では、電話応対や面談そのものが患者さんの安心を支える場面も多く、単純な効率化が最善とは限りません。
だからこそ、DX導入の目的は「人を減らす」ことではなく、「人の時間を取り戻す」ことに置くのが現実的です。
まずはオンライン問診・電子受付などを部分導入し、スタッフが“人にしかできない支援”に集中できる状態をつくる。
制度や流行に合わせるのではなく、自院の診療方針に合う形で、少しずつ整えることが重要です。
DXで詰まりやすいのは「何を入れるか」ではなく、「何を“人で残すか”」です。
まず、人で残したい支援(電話/面談の前後の声かけ/再診の安心設計)を1つ決め、
そのために“削るべき作業”をDXに寄せる、という順番が安全です。
まとめ
診療報酬改定は、「変化に耐えるための試練」ではなく、自院の理念と運用を再確認する機会です。
外来機能・収益モデル・DXの3点を、診療方針と照らし合わせて整えることで、制度の波に流されない経営基盤がつくれます。
- 地域の中で、自院の役割(初診/再診、紹介、支援の範囲)を明確にする
- 予約料・心理士活用などで、“支援を続けるための余白”をつくる
- DXは効率化より、“人の時間を取り戻す道具”として導入設計する
ここまで整理してきた内容は、知識として知っておけば十分なものかもしれません。
実際、多くの院長は「分かってはいる」「理解はできている」状態までは辿り着きます。
ただ、現場では――理解できたあとも、なぜか決断に踏み切れない。
判断を先送りにしたまま、同じ論点を何度も考え直している。
そんな状態が、知らないうちに続いていることも少なくありません。
もし今、考え続けているのに前に進んでいる実感が持てないと感じているなら、
一度、頭の中をそのまま言葉にして整理する時間を取ってみてもいいのかもしれません。
制度を読んだあと、「どう判断するか」で迷った方へ
制度や方向性は理解できても、現場では「自院では何を基準に決めるのか」で立ち止まることがあります。
次の2本は、制度の話を“判断”に落とすための補助線です(どちらも「正解」を押しつける内容ではありません)。
- 制度をどう“判断”に落とすかという話 (院長の判断軸)
- 正解を出さない整理、という選択 (正解を出さない整理)
ここまで読んで、もしこんな感覚が残っていたら
- 制度や方向性は理解できたが、自院ではどう判断すべきか迷っている
- 「今すぐ決めなくていいこと」と「整理すべき論点」を分けたい
- 頭の中では考えているが、一度、言葉にして整理してみたい
そう感じた方に向けて、
結論や正解を出す場ではなく、状況と考えを整理する時間として、「初回整理セッション」という形で対話の場を用意しています。
※売り込みや即決を目的としたものではありません。
ただ、もし同じ論点を数週間〜数か月考え続けている感覚があるなら、
その状態をいったん言葉にして整えるだけで、次の判断が進みやすくなることがあります。
正解を急がず、
ご自身の「納得解」で進むための整理の時間
開業準備や日々の経営のなかで、
「考えているはずなのに、なぜか前に進めない」
そんな状態が、数週間〜数か月続いていることは珍しくありません。
初回整理セッションは、答えを出す場ではなく、
いま頭の中にある論点や引っかかりを、一度言葉にして整えるための時間です。
🗂 初回整理セッション
料金:5,000円(税別)
最初に30分だけZoomで顔合わせを行い、
その後14日間、Chatworkまたはメールで整理を進めます。
例えば、こんな状態でご利用いただいています。
- 開業や経営について、何から整理すればいいのか分からなくなっている
- 制度や環境の変化を前に、自分なりの判断軸を一度立ち止まって整えたい
- 決断の前に、考えを言葉にして確認する時間がほしい
※この時点で何かを決める必要はありません。
売り込みや契約を前提とした場ではありません。
※整理を進めた結果、必要だと感じた場合のみ、
月額の伴走(開業・経営整理セッション)を選ぶこともできます: 詳細
事前に「雰囲気」を知りたい方へ
日々の診療や経営の中で生まれる、
言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、声で整理していくPodcastです。
初回整理セッションの前に、
考え方や伴走のスタンスが合いそうかを確かめる入口としてご利用ください。
※外部サービスが新しいウィンドウで開きます