財務省提言で診療所は何が変わる?院長が今からできる準備3つ(30日チェック付き)
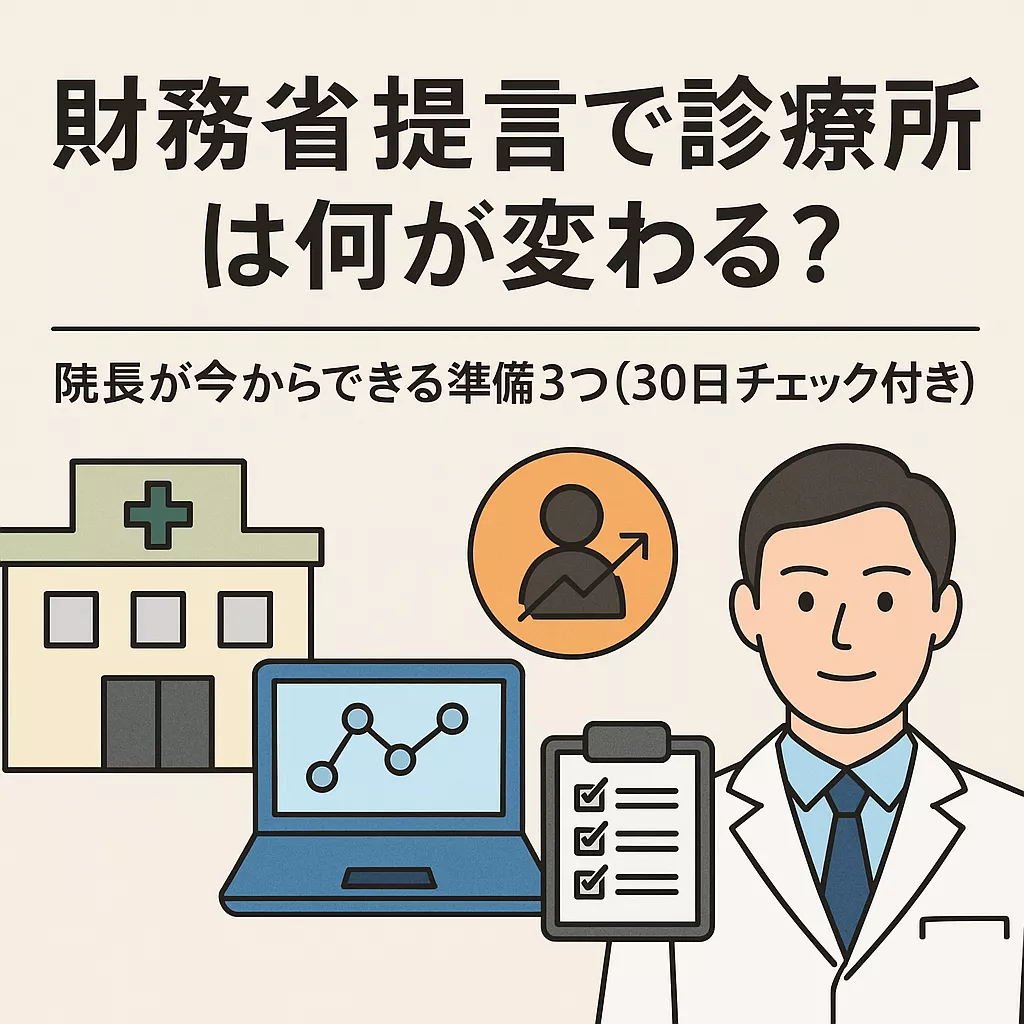
財務省の提言は、診療報酬改定の“前段”で、制度の流れを先読みできる資料のひとつです。
ただ、読んでみると「結局、診療所は何を変えればいいの?」が曖昧なまま残りがちです。
本記事では、財務省提言が診療所に与える“本当の影響”を、院長が判断しやすい形に整理し、今日から取れる現実的な経営アクションを3つにまとめます。
さらに、動き出しやすいように「30日でできる下準備チェックリスト」も付けました。
この記事の結論(先に要点)
- 財務省の提言は「点数の話」よりも、診療所の役割を“見える化”し、地域の中で位置づける方向に寄っています。
- これからの評価軸は、院長の頑張りではなく、チームで回る構造(業務分担・標準化・DX)に移ります。
- 院長が今やるべきは、制度の暗記ではなく、自院の診療体制・患者層・運用を整理し、判断基準を先に作ることです。
1. なぜ財務省は診療所に踏み込むのか?
財務省の提言は、6月頃に公表される「骨太の方針」や「財政制度等審議会」の資料を通じて、医療政策の方向性を先取りする内容になっています。
そして最近の論点は、単に医療費を抑えるという話に留まらず、“地域で医療をどう回すか”の設計に踏み込んでいます。
2026年度に向けて注目すべき論点は、概ね次の3つです。
- かかりつけ医機能の明確化(役割の可視化・連携の強化)
- 医療DXの推進とデータ活用(標準化・情報共有・業務効率)
- 人件費と生産性のバランス(賃上げ局面での運用設計)
ここで重要なのは、これらが「点数の増減」だけではなく、診療所の“地域での役割の再定義”を含むことです。
すなわち、どの患者層を支え、どのように地域とつながるのかという立ち位置が問われています。
2. 診療所にとっての“本当の影響”とは?
提言を現場に落とすと、影響は大きく2つに分けられます。
ひとつは「何をしている診療所なのか」を説明できる状態が求められること。もうひとつは、人が増えない前提で、どう回すかです。
影響①:役割の“説明責任”が上がる
「かかりつけ医機能」「病診連携」「地域で支える」といった言葉は、以前から出ていました。
ただ今後は、これらを院内の運用(診療体制・対応範囲・連携)として“見える形”にしているかが問われやすくなります。
つまり、制度が変わったときに慌てるのではなく、自院の役割を言語化しておくこと自体が防御力になります。
影響②:「院長の頑張り」から「チームで回る構造」へ
再診料中心の診療科では、限られた時間でどう価値を生むかが一段と重要になります。
評価の軸は「時間短縮」から、チームでの仕組み化・分担の明確化へシフトしています。
財務省の視点では、医療費の抑制だけでなく人件費と生産性のバランスが重視されます。
つまり、これからの診療所経営は「点数を上げる」よりも、限られた人員で成果を出す構造をつくる発想が求められます。
「制度の方向性は理解できた。では自院は何から着手すべきか?」
そんなときは、まず“もやもや”を言葉にする時間をつくりませんか。
▶ 初回整理セッションを申し込む
3. 院長が今からできる3つの準備
ここからは「読んで終わり」にならないように、院内で着手しやすい順に整理します。
ポイントは、“制度対応”ではなく、“自院の判断基準を先に整える”ことです。
- 診療体制と患者層の整理:
支える患者層(慢性疾患・高齢者・在宅連携・健診等)を棚卸しし、自院の役割を一文で説明できる状態にする。
その上で、外来機能報告制度などで求められる“立ち位置”を確認する。 - スタッフ・ICT体制の再設計:
業務の属人化を減らし、受付・看護・院長の役割分担を「できる/できない」ではなく「どこまで任せるか」で決め直す。
医療DXは“導入”が目的ではなく、情報共有・二度手間削減・ミス予防につながる形に整える。 - 情報発信の整備:
取り組みは「やっているのに伝わらない」と、評価や連携の場面で損をします。
自院の役割・対応範囲・連携方針を、HPや院内掲示で患者・地域・紹介元に伝わる形にする。
改定対応は「点数表の読み解き」に終始するのではなく、自院の方向性を再確認する機会として捉えるのが効果的です。
提言を先読みし、判断基準を早めに整えることで、次の一手を自信を持って決められるようになります。
📋 30日でできる下準備チェックリスト(5項目)
- 自院の「かかりつけ医機能」を整理し、外来機能報告書の記載内容を見直す
- 主要加算の算定状況をExcel等で可視化し、算定漏れ・運用課題を洗い出す
- 職員会議で「2026年改定」に向けた意識共有(役割分担・優先順位)を行う
- ICT・DXツール(カルテ連携・情報共有・院内オペ)の活用状況を点検する
- 院長メッセージとHP発信文の方向性を確認し、地域における役割を明文化する
※これらを一つひとつ確認していく過程そのものが、改定に備える時間になります。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。
考えを整理したい先生へ——声で届ける「経営の迷いを整える」Podcast
日々の診療や経営の中で感じる、「ちょっとした違和感」や「言語化しづらいもやもや」。
そうしたテーマを、私が声で丁寧に紐解いていく番組です。
初回整理セッションの前に、私の考え方や伴走のスタンスを知りたいという先生にもおすすめです。
※外部サービスが開きます