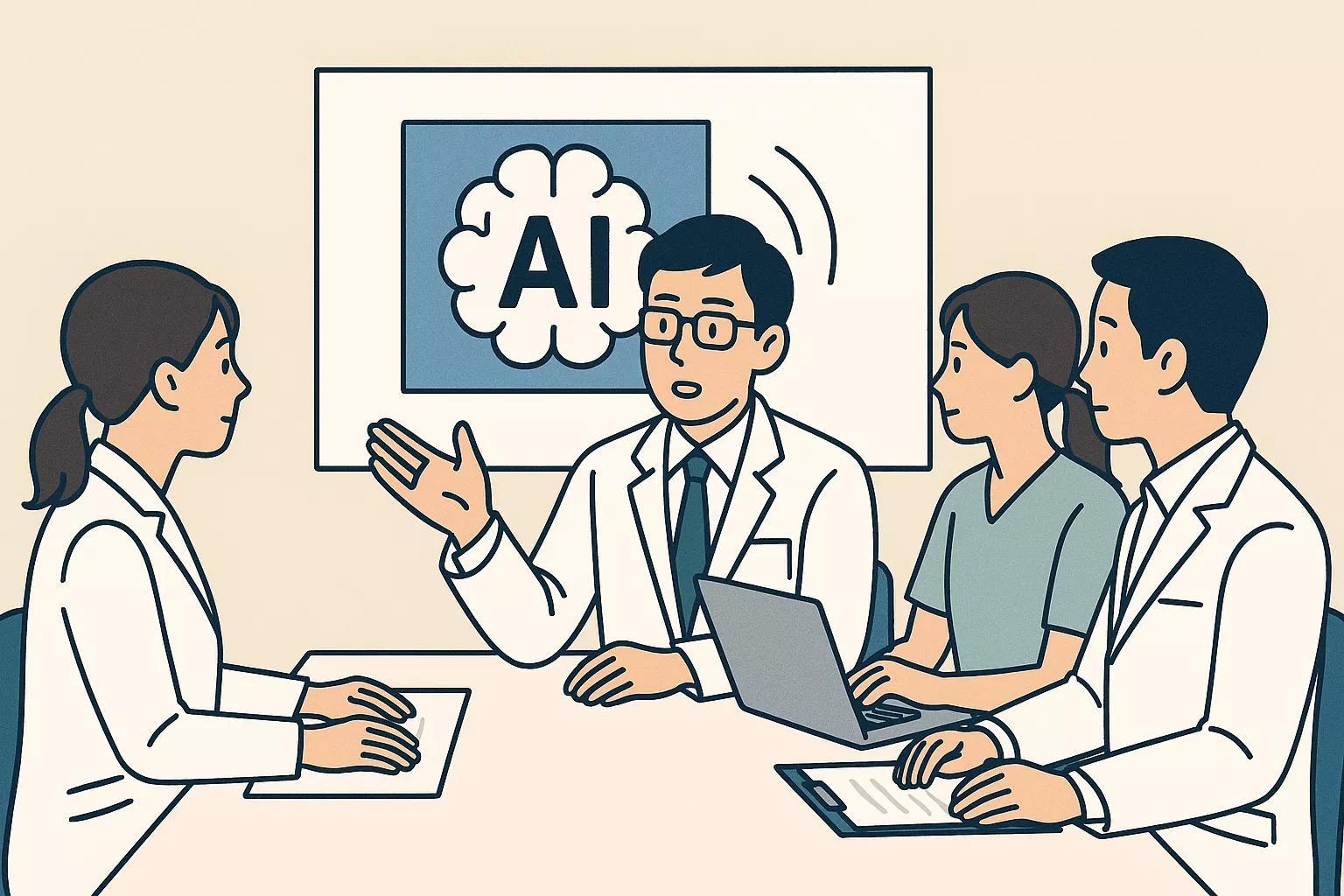文章作成・資料整理・情報収集など、生成AIの活用が広がっています。
院内掲示やお知らせ文の下書きなどに使えば、残業削減や業務効率化にもつながります。
しかし、ルールを設けずに使い始めると、情報漏えい・誤情報の拡散・著作権侵害といった経営リスクを招くこともあります。
本稿では「導入しない/使わない」ではなく、安全に活かすための考え方と実務上の注意点を整理します。
1. 個人情報・医療情報は絶対に入力しない
多くの生成AIは外部サーバー上で動作し、入力内容が保存・学習に利用される可能性があります。
患者個人情報や診療内容を入力することは、個人情報保護法や医療情報ガイドラインに抵触するおそれがあります。
試す際は必ずダミー情報を用い、ログが残る点をスタッフにも共有しましょう。
2. 出力は“下書き”と位置づけ、人が必ず確認する
AIの出力は一見整っていますが、医学的に誤りや誤解を招く表現を含む場合があります。
掲示物・院内資料・患者説明文に転用する際は、必ず人の最終確認を経てください。
責任の所在を明確にしたチェック・承認フローを決めておくと安心です。
3. 著作権と表現上のリスクを理解する
生成AIは既存著作物に似た表現を出力する場合があります。
無確認で公開すると、著作権侵害や信用の失墜につながるおそれがあります。
「誰が確認したか」「どこまで利用するか」を明文化し、用途を限定した運用を徹底しましょう。
4. 院内ルールを整備し、属人化を防ぐ
- 入力禁止情報の明確化(個人情報・医療情報は入力しない)
- 出力物は確認・修正・承認を経て使用(責任所在を明確に)
- 利用ツールは院内指定に限定(ログ管理を含む)
- 版数管理・改訂履歴を残す
これらを明文化しておくことで、スタッフが安心して使え、特定の担当者に依存しない持続可能な運用体制につながります。
5. 導入は“小さく始めて、振り返る”
まずはリスクの低い業務から試し、効果や課題を共有しながら少しずつ広げていくのが現実的です。
たとえば、院内掲示の案文づくりや会議議事録の整理などから始め、運用ルールをブラッシュアップしていきましょう。
小さな成功体験の積み重ねが、AI活用の文化を定着させます。
まとめ:技術よりも、“使い方の文化”を整える
生成AIは、人手不足下の業務効率化に役立つ一方、扱い方を誤ると信頼を損なうリスクもあります。
導入の鍵は、「入力禁止の徹底」「最終確認の仕組み」「院内ルールの整備」です。
AIを導入すること自体が目的ではなく、院内の考え方を共有し、信頼を守る仕組みづくりが本質です。
「便利さ」と「安全性」のバランスを取りながら、貴院らしい形を見つけてください。
関連記事
・クリニックのAI活用入門|人手不足でも“余裕をつくる”少人数経営の始め方
・院長が設計する、現場から始める医療DX|“持続可能な経営”を実現する5ステップ
・クリニック採用に新しい視点を|生成AIスキルをどう見極めるか
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。