院長が設計する、現場から始める医療DX ― “持続可能な経営”を実現する5ステップ ―
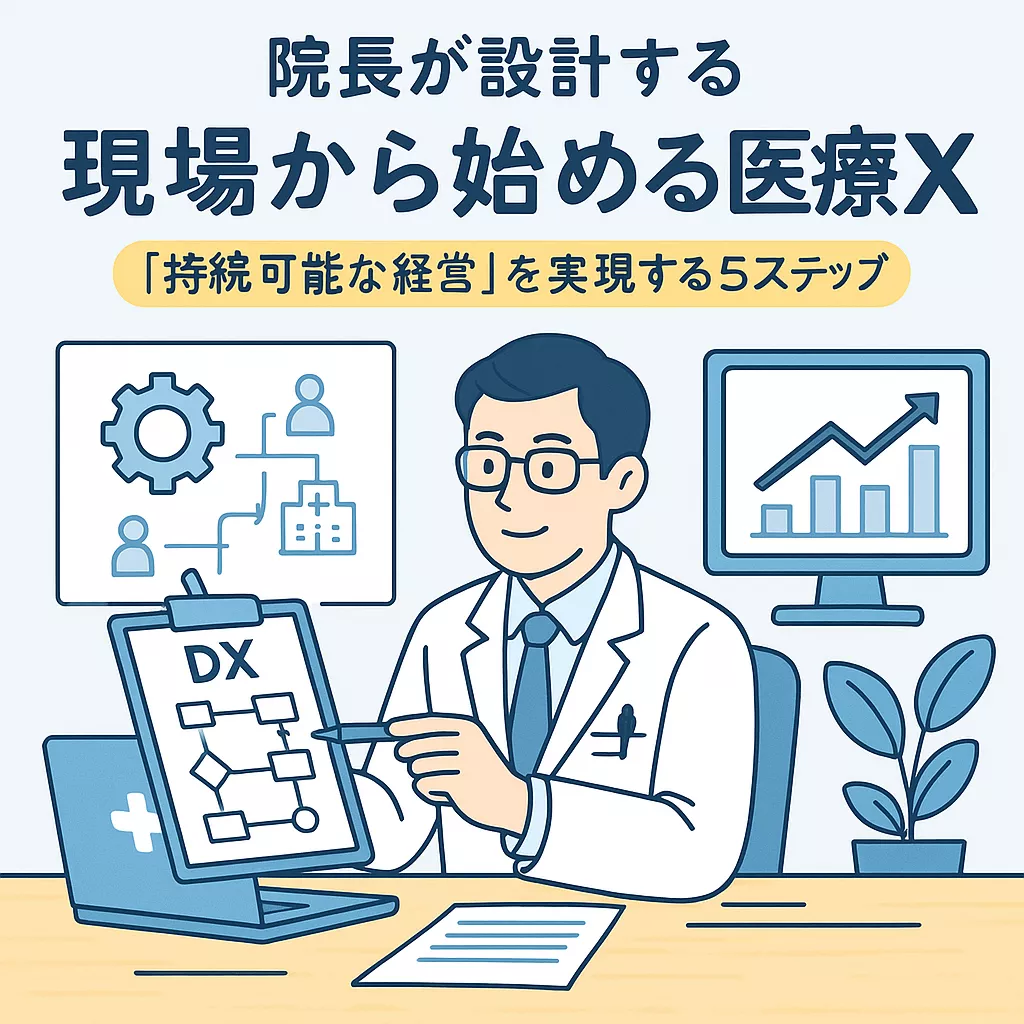
「DX=高価で難しい」と感じる必要はありません。本来の医療DXは、経営課題を現場で解くための仕組みづくり。まずは次の3つをチェックしてみてください。
読者自己診断(3点)
- 導入ツールが誰の困りごとを解決しているか説明できる
- 現場で“使えているか”を週1で確認している
- 効果(時間短縮・離脱減少・満足度)を数字で見える化している
1つでも「No」なら、“入れるDX”から“設計するDX”へ。
1.DXとは「課題を解くための現場設計」
- 意味:デジタルで、現場の回り方をより良く変える
- 狙い:待ち時間・電話滞留・会計の詰まりなどの“ムリ・ムダ・ムラ”削減
- 前提:導入前に「誰の・何の困りごとか」を言語化
メモ:ツールの前に対話。課題の言語化が成否を分けます。
2.クリニックDXの「標準装備」
| 項目 | 主な効果 |
|---|---|
| Web問診 | 受付と診察の時間を短縮し、問診漏れを減らす |
| オンライン予約 | 電話本数を減らし、来院ピークを平準化 |
| 自動音声案内(IVR) | 問い合わせを一次振り分け、対応効率を改善 |
| SMSリマインド | 予約忘れによる未受診を抑制、来院率向上 |
| セルフ会計・キャッシュレス | 会計の滞留を解消、締め作業の負担軽減 |
| 電子サイン・電子同意 | 紙のやり取り・保管コストを削減 |
コツ:数を増やすより優先順位。まず「効果が高く手間が低い」所から。
3.集患×DX:患者の体験を“切れ目なく”つなぐ
- 見つける:HP・マップ・検索情報を統一、診療内容と予約導線を明確化
- 予約:各ページに「このまま予約」を設置し、クリック数を最小化
- 来院前:Web問診+SMSで案内を自動化
- 来院時:受付案内を見える化、IVRと連携して混乱を防止
- 会計:セルフ精算・キャッシュレスでスムーズに
- 再来:次回目安の提示+必要時のSMSフォロー
4.進め方:課題 → 優先順位 → 道具 → 運用 → 振り返り
- 課題の見える化:誰のどんな困りごとか(例:受付滞留、会計詰まり)
- 優先順位の決定:いま一番効く所から着手(合意形成)
- 道具選び:目的適合性と現行運用との親和性を確認
- 導入と教育:手順書+ミニ動画+初週の濃いフォロー
- 振り返り:時間・件数・満足度の3指標で効果検証(90日で判定)
優先順位づけ(効果×手間の目安)
効果大×手間小:Web問診の徹底/予約導線の1クリック短縮/SMS案内
効果小×手間小:HP文言の更新/院内表示の微修正
効果大×手間大:セルフ会計導入/IVR再設計/電子サイン運用
効果小×手間大:在庫連携・広域統合は必要性を精査
5.90日で小さく始めるプラン
- 週1・30分の観察:混雑帯で受付〜会計の詰まりを記録
- 即効施策を1つ:Web問診定着/予約導線短縮/IVRメニュー見直し
- 短時間の増援:ピーク2〜4時間の支援枠で属人化を外す
- 連絡ルール:問い合わせ・合否連絡は当日〜翌営業日
- 数で確認:待ち時間/電話件数/会計締め時間の3つを毎週レビュー
6.チェックリスト(抜け取り用)
- 課題が誰の何かで表現できている
- 優先順位がチームで共有されている
- 道具は目的適合・運用親和が取れている
- 手順書とフォロー体制がある
- 効果を示す3指標を毎週確認している
まとめ
医療DXはIT導入ではなく、経営設計の手段です。小さく始め、90日単位で確実に現場を軽くする――それが、結果として持続可能な経営につながります。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
DXは現場の回り方から。初回整理セッションでは、課題の言語化→優先順位→90日プランまで、院内の実情に合わせて一緒に組み立てます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。