心療内科・精神科経営シリーズ 第2回|臨床心理士をどう活用するか
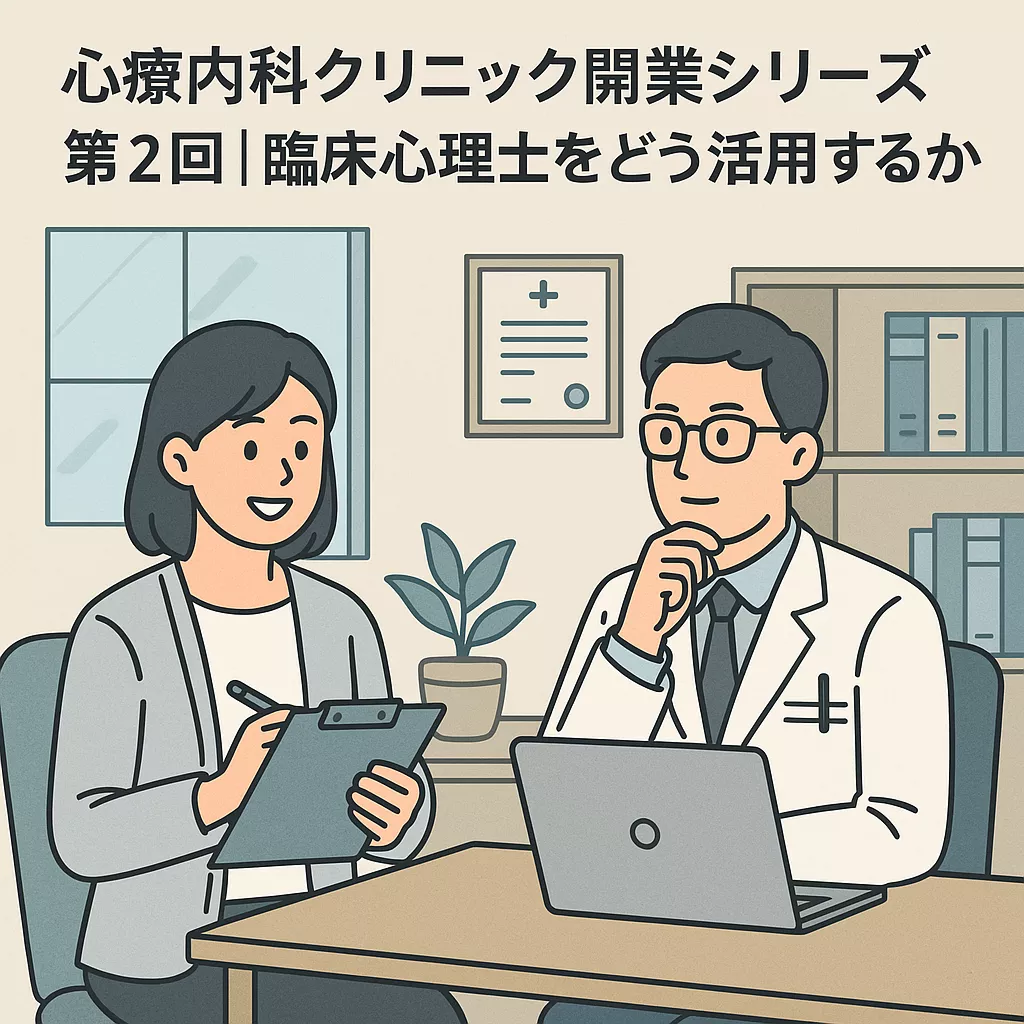
本記事は「診療科目別経営戦略/心療内科・精神科経営シリーズ」に属します。
臨床心理士(公認心理師)の採用・稼働・収益化・院内連携を、現実的な運用視点で整理しました。
心療内科・精神科経営シリーズ 第2回|臨床心理士をどう活用するか
医師1名体制が多い心療内科では、診られる人数や収益に上限が生まれがちです。
その限界を補い、診療の幅と支援の質を高める存在が臨床心理士です。稼働が安定すれば、診療効率だけでなく、経営の持続性にもつながります。
本記事では、採用・稼働・収益化・連携という4つの観点から、各院の診療方針にフィットする活用の道筋を示します。
1. 採用のポイント
まずは雇用区分(常勤/非常勤)・経験年数・専門領域(例:発達支援、CBT、うつ・不安、産業メンタルヘルス等)を明確化し、地域相場に沿った条件設定を行いましょう。
採用難易度や募集チャネルは地域差が大きいため、求人媒体+信頼経由(学会・研究会のネットワーク、既存のつながり、紹介)を併用すると、ミスマッチが減ります。
募集要件は「できると望ましい業務」を欲張らず、自院で確実に運用できる業務から始めるのがコツ。
例)「WAIS等の基本的な検査」「個別カウンセリング」「医師との症例カンファ」など、最小構成から段階的に拡張します。
2. 稼働と収益性
心理士が担える主な業務は、心理検査(例:WAIS等)、個別カウンセリング(精神科専門療法)、集団療法の補助など。
稼働率=収益性に直結するため、予約枠の設計(長さ/回数/キャンセル規定)と案内導線(診察室→受付→会計・次回予約)が鍵になります。
料金モデルは、保険算定の最大活用+自費カウンセリング/自費検査の適切な設計が基本です。
外部需要とつなぐ選択肢として、産業医契約や学校・企業との面談スキームを一部受託する方法も有効です。いずれも、患者層・地域性・人員体制に合わせて段階的に整えるのが現実的です。
3. 経営・組織への影響
心理士が関わることで、医師は医師にしかできない診療に集中しやすくなり、心理面のフォローは心理士が担う体制が構築できます。
医師×心理士×事務のチーム連携が整えば、説明の一貫性・安心感が高まり、通院継続率や満足度の向上が期待できます。
現場運用に落とす際は、役割分担とプロトコルの文書化が必須です。
初診→検査→介入→再診の各フェーズで「誰が何をどこまで行うか」「次に誰へ引き継ぐか」を明確にし、受付・会計まで一貫させます。
4. 導入時の留意点
導入初期はコスト先行・稼働不足になりがちです。
①紹介経路の整理(医師説明・パンフ/院内掲示)、②予約枠の段階拡張、③キャンセル規定とリスケ運用をセットで設計し、枠を「育てる」発想で進めましょう。
また、医師と心理士の境界(初診・再診・検査・介入)が曖昧だとフローが混乱します。
患者向けにも、「心理士によるカウンセリングは医師の診察と組み合わせて行う」等の方針、費用・時間・目的を事前に明記し、納得感を高めましょう。
まとめ
臨床心理士の活用は、心療内科クリニックの診療の幅と経営の持続性を同時に高めます。
地域の採用難易度やコストを踏まえつつ、役割分担を明確にし、稼働が安定するまでの育成設計を組み込むことが鍵です。
各院の診療方針と地域の実情に合わせ、無理のない範囲から始めましょう。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。