日本医師会調査から見える“2030年の診療所経営”|開業医がいま備える5つの視点
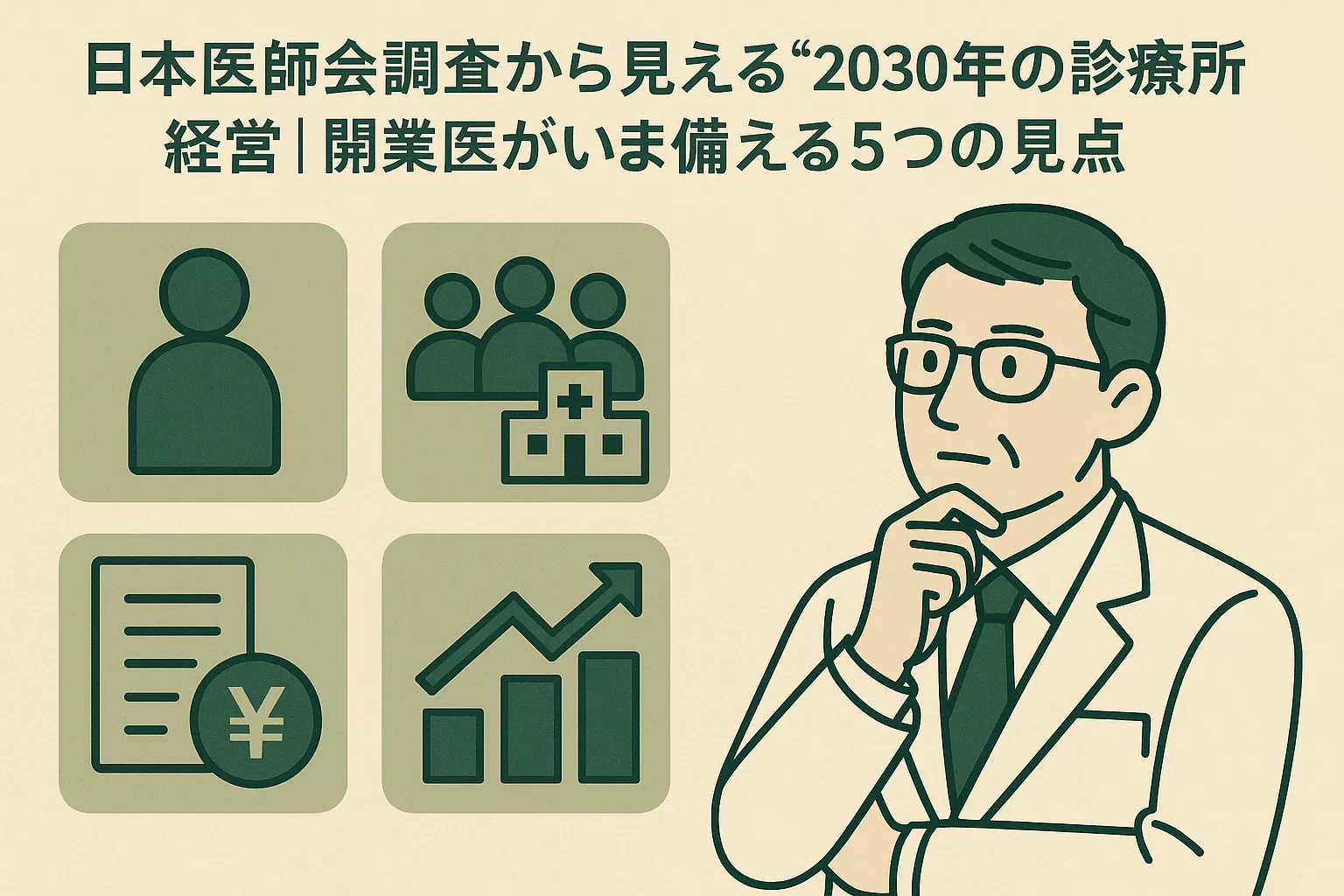
本記事は、令和7年(2025年)9月17日に日本医師会が発表した『令和7年 診療所の緊急経営調査 結果 ― 令和5・6年度実態報告』[1]をもとに、「現場の肌感覚」と「データの示す傾向」をつなぐ視点でまとめています。
調査では、物価・人件費の上昇、患者数の減少、診療報酬の伸び悩みなどにより、多くの診療所で利益率が悪化している実態が明らかになりました。
こうした変化のなかで問われているのは、「何を守り、どこを変えるか」という経営判断です。
1.人件費と採用難 ― “給与以外”の価値づくり
スタッフ確保と定着は、今後さらに厳しさを増します。給与だけで人を引き留める時代は終わり、働きやすさ・やりがい・職場文化の有無が採用競争力を左右します。
放置すれば経営の根幹が揺らぐ一方で、WEB予約・AI電話・自動精算機などのDXツールを活用すれば、限られた人員でも運営できる仕組みづくりが可能です。
目先の採用戦略にとどまらず、「人が辞めにくい仕組み」と「人が育つ風土」の両輪を整えることが重要です。
2.患者数・受診行動の変化 ― “潜在ニーズ”を掘り起こす
少子高齢化や受診控えの流れを踏まえ、生活習慣病外来・高齢者外来・健診異常フォロー・ポリファーマシー対応など、潜在的な需要を拾う体制づくりが求められます。
「まずはこのクリニックへ」と思ってもらえるよう、かかりつけ医機能を明確に打ち出すことも重要です。
患者数の減少を嘆くよりも、「来院理由の変化を読み解き、行動設計を変える」視点が鍵になります。
3.診療報酬一本足からの転換 ― “制度依存”のリスク管理
制度改定は数年ごとに行われ、診療所経営に直接影響を及ぼします。特に2026年度改定以降は、医療DX・チーム医療・地域連携が中心テーマになる見込みです。
この変化を見据え、自費診療・産業医・在宅・予防プログラムなど複線化を図ることが、中期的な安定につながります。
診療報酬を“軸”に据えつつも、“依存”しすぎない構造を意識することが、経営のリスク分散です。
4.設備・資金・承継 ― “未来の更新”を前倒しで考える
建物や医療機器の老朽化は、どのクリニックにも必ず訪れます。更新のタイミングで慌てないために、リース・購入の判断基準や、省エネ型設備への転換を早めに検討しておきましょう。
このような「未来の更新」に備える考え方は、設備だけでなく、経営そのものをどう引き継ぐかという視点にもつながります。
たとえば、数年後のスタッフ体制や患者層の変化を見据え、どんな形で診療所を残していきたいかを少しずつ言語化しておくこと。これは、経営者が自院の未来像を整理する「第一歩」です。
なお、事業承継・M&Aのスキーム設計や仲介などの専門実務は当社の支援範囲外となります。
実務的な手続きやスキーム検討が必要な場合は、税理士・金融機関・専門仲介機関など、適切な専門家への相談をお勧めします。
当社がサポートできるのは、院長先生が将来像・前提条件・価値観を整理し、「どう続けたいか」を言葉にする段階です。
診療所を“残す”ことは、経営者個人の出口戦略であると同時に、地域医療の継続を守る行動でもあります。焦らず、日々の経営の延長線上で考えていくことが、最も現実的な準備です。
5.まとめ ― “待つ経営”から“準備する経営”へ
2030年は、まだ少し先のように感じます。しかし、人・患者・制度・資金・地域の5つの要素は、すでに変化を始めています。
「変化を予測する」よりも、「変化を前提に設計する」。この視点こそが、これからの経営に求められる態度です。
小さくてもよいので、今日から“準備”を始めましょう。未来を“待つ”のではなく、自らの手で整えていく姿勢が、四方よし(患者・地域・スタッフ・自分)の経営につながります。
参考資料
- 日本医師会『令和7年 診療所の緊急経営調査 結果 ― 令和5・6年度実態報告』(2025年9月17日)
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20250917.pdf - 日医総研ワーキングペーパー No.494『令和7年 診療所の緊急経営調査』(2025年9月9日)
https://www.jmari.med.or.jp/wp-content/uploads/2025/09/WP494.pdf
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。