診療報酬制度が変わる今、院長に求められる「経営の視点」とは
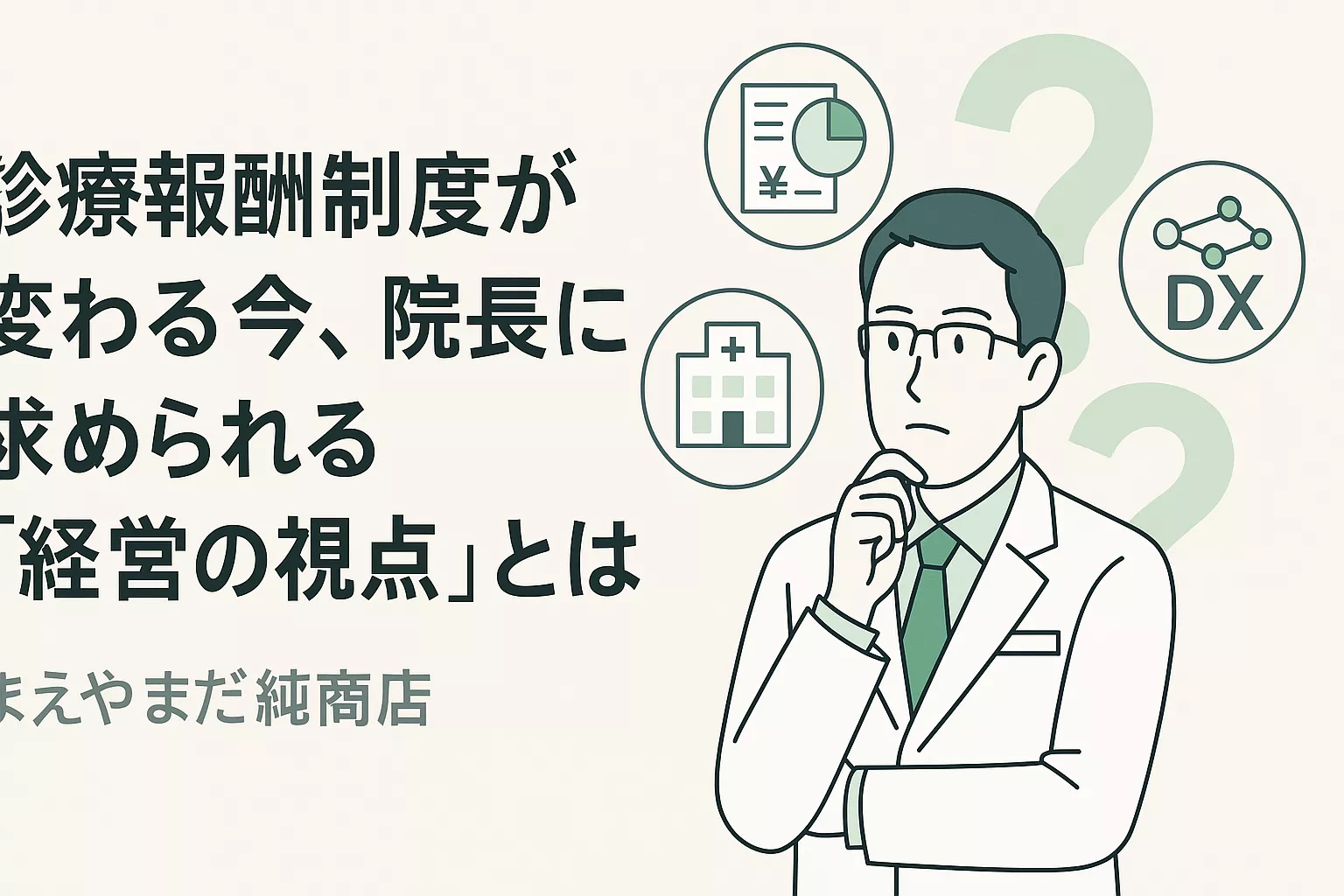
本記事は「クリニック経営の基本視点」シリーズの一つです。
医学部や研修では学ぶ機会の少なかった「経営の考え方」を、制度や現場の視点から整理しています。
なぜ「経営」を学ぶ機会が少なかったのか
医学部や研修では、診療や研究に集中します。解剖学・病理学・臨床実習など膨大なカリキュラムを経て国家試験に合格する――
医師にとっては「良い医療を提供すること」こそが最大の使命であり、経営やマネジメントを体系的に学ぶ時間はほとんどありません。
結果として、「医療の質=医師としての評価」となる文化が根づき、経営という言葉はどうしても遠く感じられてきました。
制度と環境がもたらした“安心構造”
日本には国民皆保険制度があり、診療報酬は全国一律で定められています。かつては、患者さんの数さえ確保できれば診療を続けるだけで一定の収益が得られる仕組みでした。
さらに、地域によっては医療機関が少なく、「近隣に開業すれば自然と患者が集まる」という時代もありました。
制度と地域環境が医師を守る“安心構造”を形成していた――それが、経営を深く考えずとも成り立っていた背景です。
経営者意識が芽生えにくい3つの要因
- 「経営=お金儲け」と見られることへの抵抗感
- 院長自身がプレイヤーと経営者を兼務しており、物理的に時間が足りない
- 経営の悩みを相談できる相手が限られている
これらは、個人の努力不足ではなく「構造としてそうなりやすい環境」があったと言えます。
一般の起業家との違い
経営を学ぶ機会が少ないのは、実は医師だけの話ではありません。
多くの起業家も、学校で経営を体系的に学んできたわけではないのです。
ただし、一般の起業家は市場競争に晒されることで「学ばなければ生き残れない」と早く気づきます。
一方で医師は、制度に守られた安定的な環境の中で診療に専念できる期間が長く、経営に目を向ける機会が少なかった――この違いが今日のギャップを生んでいます。
まえやまだ純商店の視点
まえやまだ純商店では、「依存させない伴走型支援」を掲げています。
経営リテラシーが生まれにくい背景を理解したうえで、院長先生ご自身の考えを整理し、次の一歩を形にする壁打ち相手として伴走します。
「判断は院長先生、当社は整理と実行の伴走役」。
この立ち位置を明確にすることで、先生が専門である診療により集中できる環境づくりを支援しています。
おわりに ― “意識の芽”を育てる段階へ
これまで経営を意識してこなかったのは、教育・制度・環境から見れば自然な流れです。
しかし近年は、診療報酬制度が体制整備やマネジメントを前提とする方向に進んでおり、「医師」としての専門性に加え、「経営者」としての視点も欠かせません。
まずは「なぜ経営を考える必要があるのか」を理解することから。
それが、次のステップ(制度の構造を知る)へとつながります。