電気代・人件費・材料費…上がり続けるコストにどう備えるか|物価高時代の医療経営
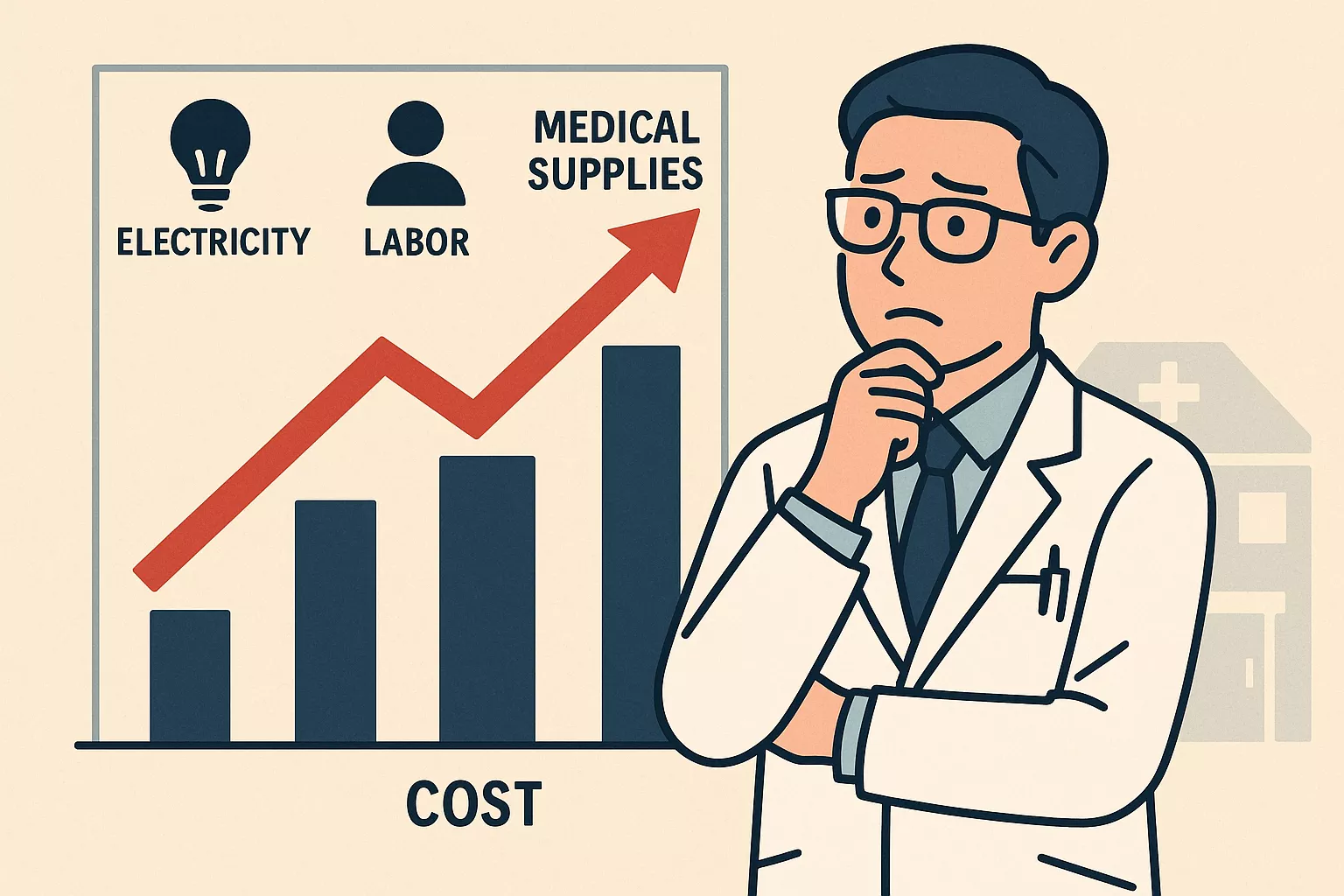
電気代、医療材料費、消耗品、人件費——。ここ数年の物価高で、こうしたコストが少しずつ、しかし確実に重くなってきています。「前よりも負担が増えている気がする」「このままでは余裕がなくなるのでは」と感じている院長先生も多いのではないでしょうか。
保険診療は価格転嫁が難しい以上、「診療の質は守りながら、どこで効率化するか」が経営のポイントになります。本記事では、物価高が医療経営に与える影響を整理したうえで、クリニックが今すぐ取り組める見直しポイントをまとめます。
現場の声:
「電気代がじわじわ効いている」「材料費と人件費が両方上がっている」「これ以上、何を削ればいいのか分からない」──こうした声は、決して一部のクリニックだけのものではありません。
物価高が医療経営に与える影響を、まず“全体像”で捉える
物価高というと電気代ばかりが話題になりますが、実際には複数の項目が同時に上昇しています。
- エネルギーコスト:電気代・ガス代・空調費など、止めることができない固定的な支出。
- 医療材料・消耗品:検査キットやディスポ製品、衛生用品などの単価上昇。
- 人件費:採用難・定着支援・教育コストの増加に伴う、人件費全体の押し上げ。
それぞれを単体で見ると「少しの値上がり」に見えても、積み重ねると大きな負担になります。また、こうした傾向は自院だけの問題ではなく、全国的に広く見られる動きです。
さらに、2026年の診療報酬改定では、加算の再編や基準の見直しが想定されており、物価高の影響は制度面にも波及する可能性があります。「物価高」だけでなく「改定」との組み合わせで現状を捉えておくことが、今後の判断の前提になります。
“削れないコスト”と“削れるコスト”を分けて考える
物価高への対策として「コスト削減」という言葉が先に立ちがちですが、医療現場ではすべてのコストを一律に削ることはできません。むしろ、「どこは守るべきか」「どこなら見直せるか」を分けて考えることが重要です。
削れないコストの代表は、診療の質や安全性に直結する領域です。感染対策や必要な人員配置、一定以上の材料品質、教育・研修などは、短期的な負担感はあっても、中長期的にはクリニックの信頼と安全を支える投資とも言えます。
一方で、見直せるコストとしては、次のようなものが挙げられます。
- 紙運用・手書き・二重入力などの事務負担
- 院内動線の非効率(無駄な移動や待ち時間の発生)
- 在庫管理の曖昧さによる過剰在庫や破棄
- ルールが決まっておらず属人的になっている業務
これらは、小さな見直しでも効果が積み上がりやすい部分です。「何でも削る」ではなく、「守る領域」と「変える領域」を切り分けることが、物価高時代の経営を考える第一歩になります。
クリニックが“今すぐ”行える5つの見直しポイント
ここからは、物価高の中でも診療の質を保ちつつ、クリニックが今すぐ取り組める実務的な見直しポイントを整理します。
在庫・材料・医薬品の適正化
在庫は「足りないと困る」という理由で、どうしても多めに持ちがちです。しかし、この「少し多め」の積み重ねが、月ごとの材料費のブレを大きくしていることも少なくありません。
まずは、直近数か月の使用実績を振り返り、「どのくらい持っておくと安心か」ではなく「実際にどれくらい使っているか」を基準に考えることが、適正化の入り口になります。破棄や期限切れが多い品目があれば、そこは改善余地が大きい部分です。
ICT・事務負担・院内動線の効率化
紙運用や手書きの場面、カルテ入力の二重管理、受付〜診察〜会計までの流れなど、日々の業務の中には「必要だと思って続けているが、改めて見直すと不要な手順」というものが紛れています。
たとえば、次のような視点で院内を見直してみます。
- 紙で残している情報のうち、電子化できるものはないか
- 同じ内容を複数の場所に入力・転記していないか
- スタッフの移動距離や待ち時間が偏っていないか
ICTの導入そのものが目的ではなく、「スタッフの時間外を減らす」「患者さんの待ち時間を減らす」という観点で優先順位をつけることが、結果的に経営効率の向上につながります。
加算・地域連携の取りこぼしを防ぐ
新設・変更された加算は、理解や運用に一手間かかる分だけ、「本来算定できたものを逃している」ということが起こりがちです。物価高の局面では、こうした取りこぼしを減らすこと自体が重要な経営対策になります。
ポイントは、「いつ・誰が・どのタイミングで確認するか」を決めておくことです。診療の合間に個別に思い出そうとするのではなく、定期的に加算の見直し時間を設定したり、チェックリストをつくったりすることで、安定して算定できる仕組みが整います。
人材定着のための“役割と評価”の明確化
採用が難しい環境の中で、「スタッフが辞めないこと」それ自体が大きなコスト削減になります。離職の背景には、人間関係だけでなく「自分の役割が分かりづらい」「評価されているのかが見えない」といった構造的な要因も含まれます。
次のような項目を言語化し、共有するだけでも、スタッフの安心感は大きく変わります。
- ポジションごとの役割分担と責任範囲
- 評価の基準(何ができれば評価されるのか)
- 成長のステップ(どのようにスキルアップしていけるか)
働きやすさと続けやすさが高まることで、結果的に教育コストや採用コストの抑制につながります。
月1回の“ミニ改善ミーティング”を習慣化する
物価高の時代に必要なのは、「一度にすべてを変える大改革」ではなく、無理なく続けられる小さな改善の積み重ねです。
たとえば、月に1回、30分だけ時間を取り、次のようなテーマからひとつを選んで話し合う場をつくります。
- 在庫(過不足や破棄が多い品目はないか)
- 電気代(ピーク時間や使い方の工夫はできないか)
- 時間外(どの業務が時間外につながっているか)
- 請求差異(返戻や算定漏れが生じやすい箇所はどこか)
毎回、改善点をひとつだけ決めて翌月に振り返る。この繰り返しだけでも、半年後・1年後には、経営の安定度が大きく変わってきます。
患者さんに伝えておくべき“大切なメッセージ”
物価高の影響は、患者さんの家計にも及んでいます。そのため、「医療費を抑えるために受診回数を減らしたい」「通院を少し休みたい」と考える方が増えているかもしれません。
しかし、慢性疾患の治療を中断したり、自己判断で通院間隔を大きく空けたりすることは、結果として重症化リスクと総医療費の増加につながります。こうした点を丁寧に伝えることも、クリニックの大切な役割です。
同時に、生活習慣の改善やセルフケアは、患者さん自身の健康を守るだけでなく、中長期的には医療費と家計の両方を守る行動でもあります。「どのような点に気をつけるとよいか」を、診療の中や院内掲示、ホームページなどで発信していくことが、患者さんの安心にもつながります。
また、不安や困りごとを早い段階で相談してもらえるようにしておくことも重要です。受診前の心配事を院内の案内やホームページで解消しておくことで、「ギリギリまで我慢して、結果的に重くなってから受診する」というパターンを減らすことができます。
国や制度に求められる視点
もちろん、診療所の努力だけでは解決しきれない領域もあります。エネルギーや人件費の上昇に応じた支援の継続や、地域ごとの人口構造・医療需要に応じた資源配分は、制度側の役割です。
また、「必要な医療は守る」というメッセージが明確に示されることは、現場だけでなく、患者さんや地域全体の安心感にもつながります。理念的な表現だけでなく、「どのような医療に重点的に支援を行うのか」という具体的な方向性が示されることで、現場も将来を見通した計画を立てやすくなります。
一方で、制度の動きを待つだけではなく、「いま自院でできること」に丁寧に取り組んでいくことが、物価高の中でも経営を守る現実的な方法になります。本記事で挙げた見直しポイントは、そのための一つの視点です。
まとめ|“質を守りながら効率化する”ための最初の一歩
物価高は、クリニックの努力だけで完全にコントロールできるものではありません。しかし、診療の質を守りながら経営を安定させるために、院内でできる工夫や見直しは確かに存在します。
- 「削れないコスト」と「見直せるコスト」を切り分ける。
- 在庫・ICT・加算・人材・ミニ改善といった具体的なポイントに一つずつ取り組む。
- 患者さんには、受診継続とセルフケアの大切さを丁寧に伝える。
まずは、直近3か月分の「電気代」「人件費」「請求差異」を一枚の紙や画面に並べてみるところから始めてみてください。数字を「見える化」するだけでも、次に何を見直すべきかが自然と見えてきます。
次の一歩:「これは本当に削るべきなのか」「これは本当は投資ではないか」を見極めながら、月1回のミニ改善を続けることで、物価高の波の中でもブレにくい経営の土台が整っていきます。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
初回整理セッションでは、「質を守る」×「効率を高める」観点で現在地を言語化し、実行できる計画に整えます。即答よりも、腑に落ちる合意形成を大切にしています。