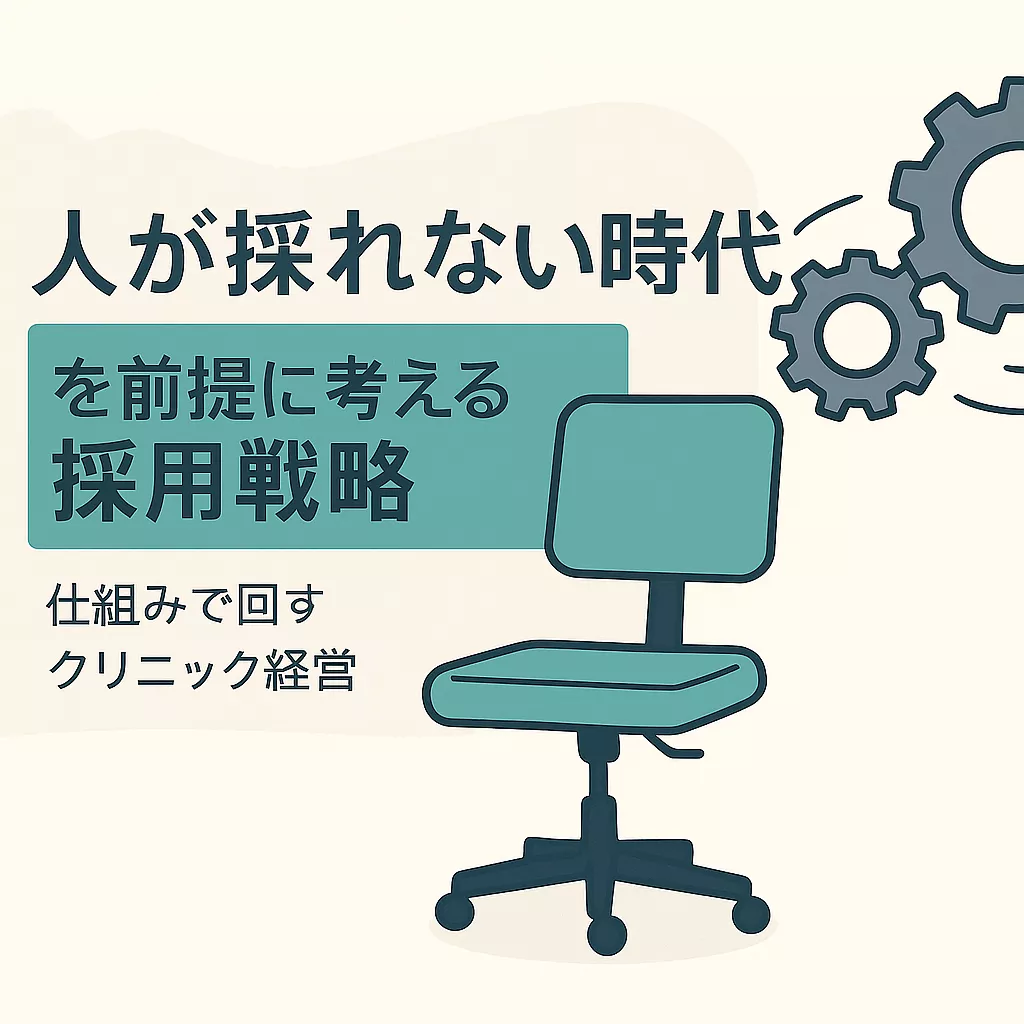スタッフが採れないのは、運の問題ではありません。医療業界全体の構造的な人手不足です。だからこそ、採れる前提ではなく、「採れない前提で設計する」ほうが現実的でぶれません。
本記事では、「人」ではなく「コト(解く課題)」から要件を定義し、業務分解・短時間設計・DX併用で現場を回すための考え方を整理します。
なぜ「採れない前提」で考えるのが合理的か
- 慢性的な需給ギャップ:医療・福祉分野は全国的に人手不足。特に有資格者は奪い合い。
- 選択肢の拡大:勤務地・雇用形態・時間の自由度が高まり、応募が分散。
- 情報の非対称性:求職者は具体情報を求めるが、多くの求人票は抽象的な表現にとどまる。
結論:採用“だけ”に依存せず、業務設計×採用×育成を同時に回す。
採用が難しくなる3つの院内要因
- 理想像の肥大化:万能人材を想定し、母集団をさらに狭めている。
- 情報不足:応募判断に必要な具体情報(外来規模・役割・評価基準など)が足りない。
- 遅いレスポンス:選考や連絡の遅れで、他院に決まってしまう。
まずは「人」ではなく「コト」から設計し、必要情報を開示し、連絡目安(当日〜翌営業日)を決めて守る。これだけで採用率は変わります。
要件定義を「人」から「コト」へ
募集の出発点を「人材像」から「課題」に変えると、採用の精度が一気に上がります。
- 課題の特定:待ち時間が長い、電話が滞留する、レセ誤りが多い等
- 役割の設計:受付導線の最適化/電話一次対応/会計精度向上など
- 成果指標:平均待ち時間◯分短縮などの目標値を明文化
- 補完計画:OJT担当・研修内容・到達目安(3か月/6か月)を設定
採れないときにやるべき設計
- 業務分解:受付・会計・電話対応・処置準備を分け、属人化を外す。
- 短時間設計:ピーク帯の2〜4時間限定枠や週2〜3日の募集で母集団を広げる。
- DX併用:Web問診、セルフレジ、自動音声案内などで人的負荷を下げる。
- 教育の標準化:動画やチェックリストで、未経験者も立ち上げやすくする。
費用対効果を「見える化」して判断する
採る・採らないを感覚で決めず、簡易な算式で検証します。
- 効果:待ち時間短縮→再来増、レセ誤り減少、追加枠の売上など
- 費用・手間:給与+採用費+教育時間−(IT導入で減る分)
- 比較:短時間雇用・外注・IT活用の三案比較で最適を選ぶ。
採用設計チェックリスト
- 採用目的が「課題(コト)」で定義されている
- 役割と成果指標が明文化されている
- 短時間・限定枠など母集団を広げる工夫がある
- IT・外注・配置転換の代替案を比較している
- 求人票が応募判断に必要な情報を満たしている
- 面接が見極め+動機形成の両輪で設計されている
- 合否連絡の目安(当日〜翌営業日)がある
- 教育の標準化(手順書・到達目安)が整備されている
- 定期的に運用を見直し、求人票に反映している
まとめ
「採れたら回る」ではなく、「採れなくても回る」仕組みを設計する。
その土台があれば、採用が“上振れ”した時に一気に伸びます。
コト起点の要件定義 → 短時間設計 → IT/外注 → 面接標準化を小さく回し、現場に落とし込みましょう。
関連記事
・応募率を上げる求人票|「たった1人」に届く書き方
・面接で“選ばれる側”になる方法|動機形成まで設計する
・クリニックのマニュアルを育てる運用の工夫
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。