診療圏調査シリーズ①:クリニックにおける「需要」を考える
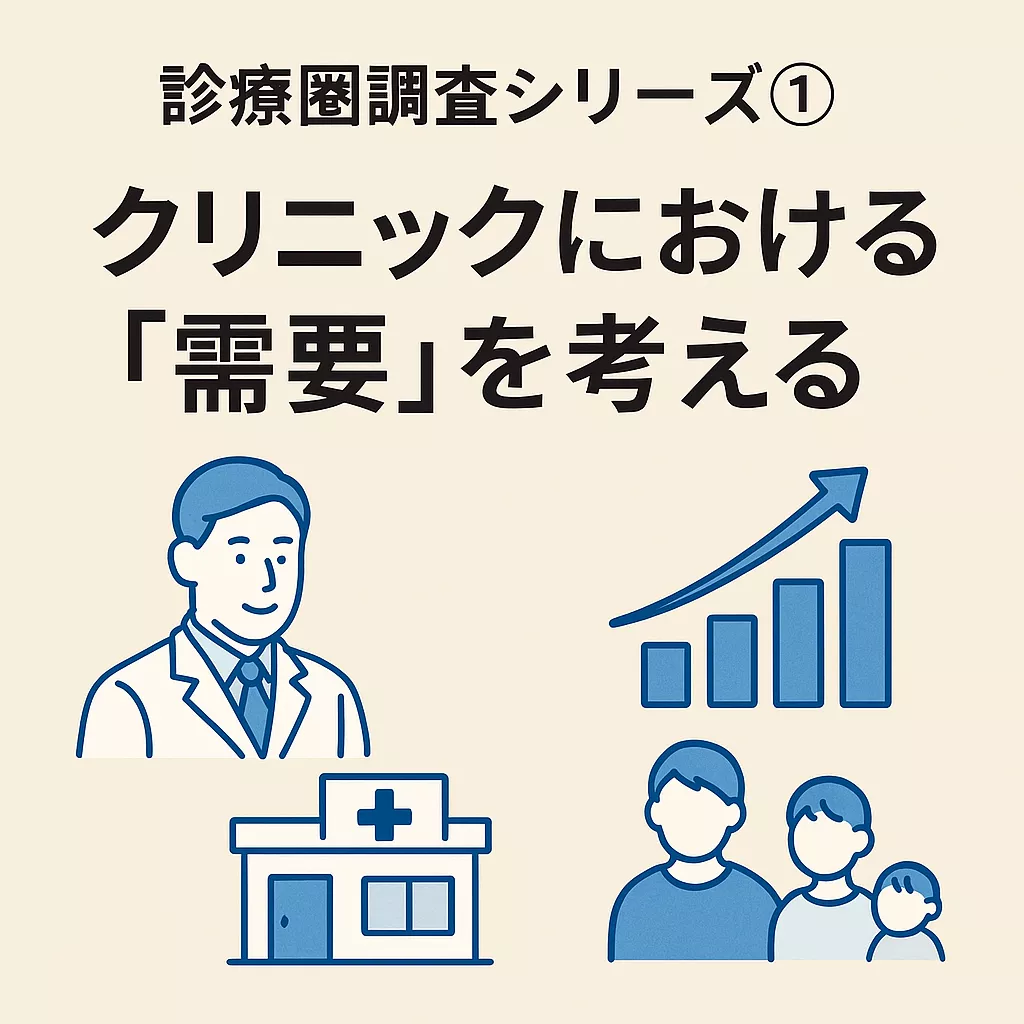
開業を検討される先生の多くが、まず気にされるのは「競合は何件あるか?」という点です。
もちろん重要ですが、その前に考えておきたいのが「需要」──つまり、その地域でどんな医療が求められているのかです。
本記事は「診療圏調査シリーズ①:需要編」として、地域ニーズを読み解く視点を整理します。
診療圏調査における「需要」とは
医療における需要とは、「地域の人々がどのような診療を必要としているか」ということです。小売業でいえば「お客様がどんな商品を求めているか」に近いイメージです。
需要を読み解く際の主な要素は、次の3つです。
- 人口構成:子どもが多いのか、高齢者が多いのか。
- 疾病構造:糖尿病や高血圧といった生活習慣病が多いのか、皮膚疾患・アレルギーが目立つのか。
- 生活背景:共働き世帯が多ければ夜間診療・予約制のニーズが高まり、外国人住民が多ければ多言語対応のニーズが生まれる。
「いま」だけでなく「将来人口」にも目を向ける
需要を考える際は、現在の状況だけでなく、5年後・10年後の変化にも注目することが大切です。
- 人口は増えるのか減るのか
- 高齢化はさらに進むのか
- 新しい住宅地・工場などで流入が起こるのか
こうした将来人口の推計は、自治体や国の統計データから確認できます。ただしあくまで予測値であり、社会変化によってズレることもあります。
“確定した未来”ではなく、“参考にできるシナリオ”として活用する意識が重要です。
勤務医と開業医では「需要」の捉え方が違う
勤務医の先生は、病院に来られる患者さんを診る立場。一方で開業を考えるときには、「患者さんがどのようにして自分のクリニックに来てくださるのか」という視点が加わります。
つまり、勤務医から開業医に移るときは「患者さんを診る」だけでなく、「患者さんに来てもらう」視点を持つ必要があります。
地域の人口構成・生活背景・将来動向を知ることが、経営の第一歩になります。
数字は「血液検査データ」、診断には背景の理解が必要
人口や将来人口などのデータは、診療圏調査に欠かせません。ただしそれは「血液検査の数値」と同じです。
血液検査は重要な指標ですが、それだけで診断を下すことはありません。症状・生活背景を合わせて初めて正しい判断に至ります。
需要データも同様に、数字だけではなく、先生の理念・診療方針・働き方と重ね合わせて考えることが大切です。
おわりに
クリニックにおける「需要」とは、単なる人口統計ではなく、地域の人々がどんな医療を望んでいるかを理解することです。
今の人口や生活背景だけでなく、将来を見据える視点が欠かせません。
ここで役立つのが、近江商人の「三方よし」の考え方です。
詳しくはこちら → クリニック開業と地域医療 ― 「三方よし」の視点で考える
- 今の需要を正しく把握する
- 将来人口の変化を読み取る
- ご自身の理念と重ね合わせる
次回は、この「需要」に対して地域でどんな医療がすでに提供されているのか──つまり「供給」について考えます。
📘 診療圏調査シリーズ
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。