診療圏調査シリーズ④:クリニックにおける「協業」を考える
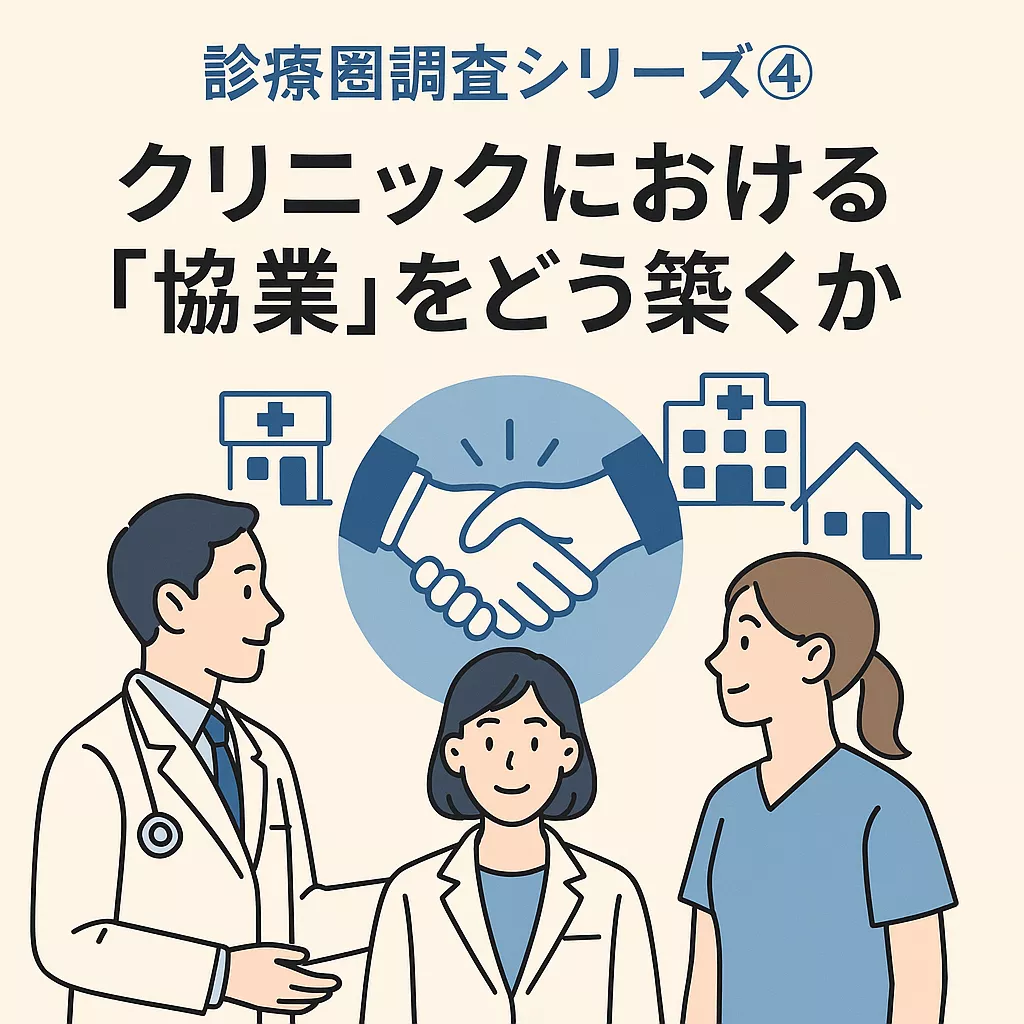
これまで「需要」「供給」「競合」について整理してきました。前回は「競合」──つまり同じ診療科を持つクリニックとの関わり方を考えました。
詳しくはこちら → 診療圏調査シリーズ③:クリニックにおける「競合」を考える
今回は少し視点を変えて、「協業」──地域で連携できる医療機関や施設との関わりについて考えてみましょう。
診療圏調査における「協業」とは
協業とは、地域の医療機関や介護・福祉施設が互いに連携しながら、患者さんの生活を支えること。
競合が多い・少ないといった“静的な比較”ではなく、どう支え合い、どう分担していくかという“動的な関係”に目を向ける視点です。
地域の中でつながりが生まれると、診療の幅も自然と広がります。
「自院で完結させる」から「地域で支える」へ──。それが、これからの診療圏の考え方です。
協業が生まれる具体的なシーン
- 診診連携: 内科と耳鼻科が連携し、かぜ・アレルギーなどの患者さんを相互に紹介。
- 病診連携: 開業医が基幹病院とつながり、画像検査や入院をスムーズに依頼。
- 在宅医療との連携: 外来中心でも在宅クリニックと協力し、途切れのない支援を実現。
- 介護・福祉との協業: ケアマネ・訪問看護・地域包括支援センターと連携し、医療×生活の支援を行う。
大切なのは、患者さんの流れ(紹介・逆紹介・相談)を「見える化」して、関係を育てていくこと。
協業は“契約”ではなく、“信頼の積み重ね”から始まります。
勤務医と開業医で変わる「役割」の視点
勤務医の先生は病院の中で診療が完結することが多く、協業を意識する機会は少ないかもしれません。
しかし、開業すると「必要な時に適切につなぐ」ことが、患者さんにとっても医療全体にとっても欠かせない役割になります。
協業を前提に考えると、先生の負担も軽くなり、患者さんが最適な医療資源にアクセスしやすくなります。
それは医療の質と経営の持続性を両立する、まさに“地域とともに歩む診療”です。
診療圏調査に「協業」の視点をどう組み込むか
診療圏調査では、周囲にどんな医療機関や施設があるかを地図やデータで把握します。
その際、競合の数を数えるだけでなく、次のような観点で「協業の可能性」を探してみましょう。
- このクリニックや病院とは、どの疾患や検査で連携できるか?
- この施設(在宅・介護・福祉)と組めば、生活面をどう支えられるか?
- 地域包括支援センター・薬局・学校・事業所と、どう情報を共有できるか?
こうした関係は、統計や地図だけでは見えません。
現地を歩く・電話で話す・地域連携室に相談する。
そんな一手間が、信頼のネットワークを生み出します。
おわりに──「競う」から「つながる」へ
「競合に勝つ」だけを目指すと、診療はどうしても短期的になります。
一方で、協業を前提にした診療圏戦略は、患者さんの継続受診や紹介の循環を生み、医療の質と経営の安定の両立を可能にします。
- 診診連携・病診連携・在宅や介護との協力を意識する
- 競合調査と同時に「協業候補」を地図化・リスト化する
- 地域ネットワークの一員として、自院の役割と導線を描く
先生のクリニックが「診療所」であると同時に、地域を支える拠点として信頼されていく。
その第一歩が、「協業」という考え方です。
📘 診療圏調査シリーズ
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。