神経内科経営シリーズ 第4回|“支える医療”を仕組みに──認知症・パーキンソン病・頭痛外来の設計視点
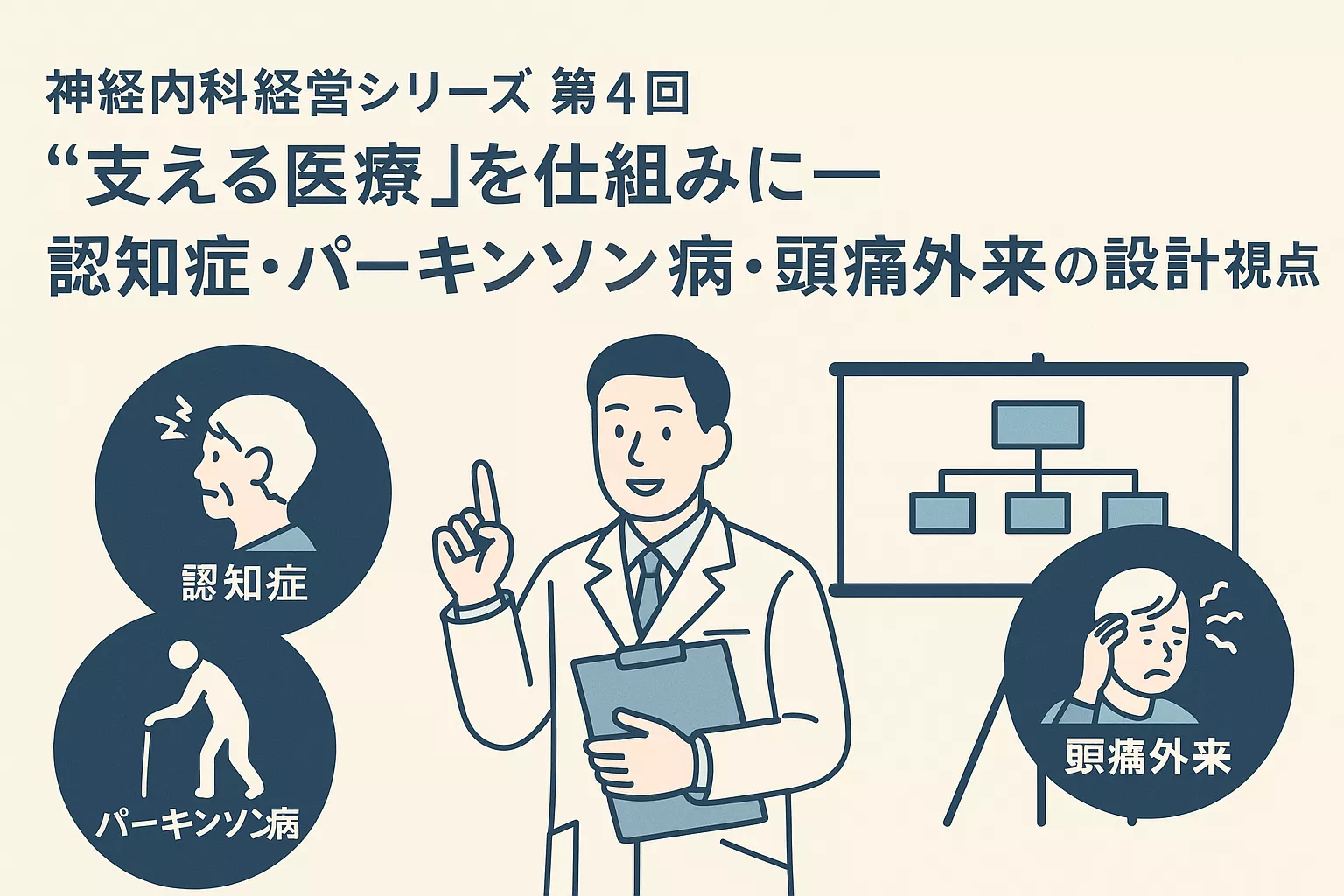
神経内科は、急性期を過ぎた患者さんと長く関わる診療科です。
その中心にあるのが、「治す」から「支える」へと移る慢性期診療。
本稿では、神経内科クリニックにおける“続けられる診療”をどう仕組みとして設計するかを、認知症・パーキンソン病・頭痛外来を例に整理します。
本記事の要点(30秒で)
- 慢性期=「通い続けられる仕組み」を整えるほど、医療の質と経営は安定する。
- 認知症は地域共助、パーキンソン病は多職種連携、頭痛外来は入口設計が鍵。
- 指標は通院継続率・平均来院間隔・診療単価を定点観測。
1. 通い続けられる仕組みが、経営を安定させる
神経内科では「一度治して終わり」ではなく、「支えながら続ける」診療が基本です。
この“続けられる構造”こそが、医療の質と経営の安定を両立させる基盤になります。
通院しやすさ、安心感、スタッフの対応、家族との関係性――。
日常の積み重ねが患者さんの「通い続ける理由」となり、紹介・口コミ・地域連携を生み出します。
慢性期診療=経営の持続性を支える装置と捉えることが重要です。
まずやる3つ(現場の最初の一歩)
- 再診のデフォルト来院間隔を疾患別に定義(例:頭痛4〜8週/PD 4〜12週)。
- 家族連絡の標準スクリプトを用意(伝える項目・緊急時ルート)。
- 初診〜再診の導線図を掲示(受付・問診・説明・次回予約)。
2. 認知症外来|地域とともに支える設計
認知症診療では、医療単体よりも地域全体での支援設計が鍵になります。
クリニックが「医療」と「生活」をつなぐハブとなることが、長期的な信頼構築につながります。
- 初診時に「何をどこまで診るか」を明確に伝える
- 介護・ケアマネ・地域包括支援センターとの情報共有を定期化
- 家族との連絡経路・面談タイミングを標準化
現場テンプレ(抜粋)
- 面談スロット:第2・第4水曜16:00–16:30/家族説明専用枠を常設。
- 共有様式:ケアマネ向け「経過共有シート」を月1送付(服薬・行動・受診予定)。
- 迷子時連絡:受付→看護→医師→家族→地域包括の順で即時連絡。
通院が長期化しやすく、家族紹介が生まれやすい点も経営面での強みです。
地域と信頼を積み重ねる“支えの設計”が、安定経営の第一歩となります。
3. パーキンソン病・神経難病外来|多職種連携を仕組みにする
神経難病は、専門性と継続性の両立が求められる領域です。
「続けやすい体制」をあらかじめ仕組み化することで、診療の質と効率を高められます。
- 通院間隔を柔軟に設定し、オンライン診療や事前Web問診を活用
- リハビリ・服薬管理・経過共有をチームで標準化
- 次回までの目標・注意点を家族にも共有
連携チェック(誰が/何を/いつ)
- 医師:治療方針と次回目標を要点メモで記載/外来終了時
- 看護:副作用チェックと生活指導を患者・家族と復唱/会計前
- リハ:在宅での運動メニューを配布し実施可否を確認/必要時
- 事務:次回予約(目安間隔内)と家族連絡先の再確認/会計時
医師一人で抱え込まず、チーム全体で支える体制を整えることで、
患者さん・家族・スタッフの“安心の輪”が広がります。
4. 頭痛・しびれ外来|“入口の設計”が支えの起点になる
頭痛やしびれの症状は、神経内科を知る“入口”となる重要なテーマです。
軽症でも相談しやすい環境を整えることで、患者層の裾野を広げられます。
- LINE予約・Web問診で初診のハードルを下げる
- ホームページで診療の流れと“次の一歩”を明確に案内
- 来院後の説明・再診導線をスタッフ全員で共有
HP掲載用テンプレ(そのまま転用OK)
「はじめての方へ:
1)まずWeb問診にご回答ください。
2)現在の痛みの頻度・強さ・服薬を記入いただくと診察がスムーズです。
3)再診の目安は4〜8週です。症状が強いときは早めの受診をご案内します。」
入口の広い診療は、紹介・再診の増加につながり、
「神経内科が身近にある」という地域認知を育てます。
5. チームが支える“仕組みの医療”へ
慢性期診療では、医師のスキルよりもチームの仕組みが成果を左右します。
次のような整理が進むと、現場が自走し、医師が経営を見通せるようになります。
- スタッフ教育:疾患理解と対応の共通認識をつくる
- 問診設計:症状別(頭痛・しびれ・めまい)で標準化
- 情報共有:電子カルテ・チャット・リハ連携の運用ルール明確化
- 経営指標:通院継続率・平均来院間隔・診療単価を定点観測
経営ミニKPI(目安)
- 通院継続率:3か月後70%/6か月後60%を目安に推移確認
- 平均来院間隔:疾患別の目標幅を設定(頭痛4–8週/PD 4–12週など)
- 診療単価:季節変動より患者単位の推移で評価
仕組みを整えることは、医師が「支える医療を続けられる環境」を整えること。
結果として、スタッフが自律的に動き、患者さんの安心が広がります。
まとめ|“治し支える医療”を経営の仕組みに
神経内科の慢性期診療は、“治し支える医療”の実践そのものです。
診療の継続を支える仕組みは、医療の質を守り、経営を安定させます。
患者さんと共に歩み続ける設計こそ、これからの神経内科経営の中核です。
院内共有ショートメモ
- 家族連絡の標準スクリプトを受付・看護に展開。
- 初診→再診の導線図をスタッフルームに掲示。
- 来院間隔と通院継続率を月次で確認、改善点を5分ミーティングで共有。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。