泌尿器科クリニック経営シリーズ 第5回 内科との連携で広がる “腎臓から見た医療”
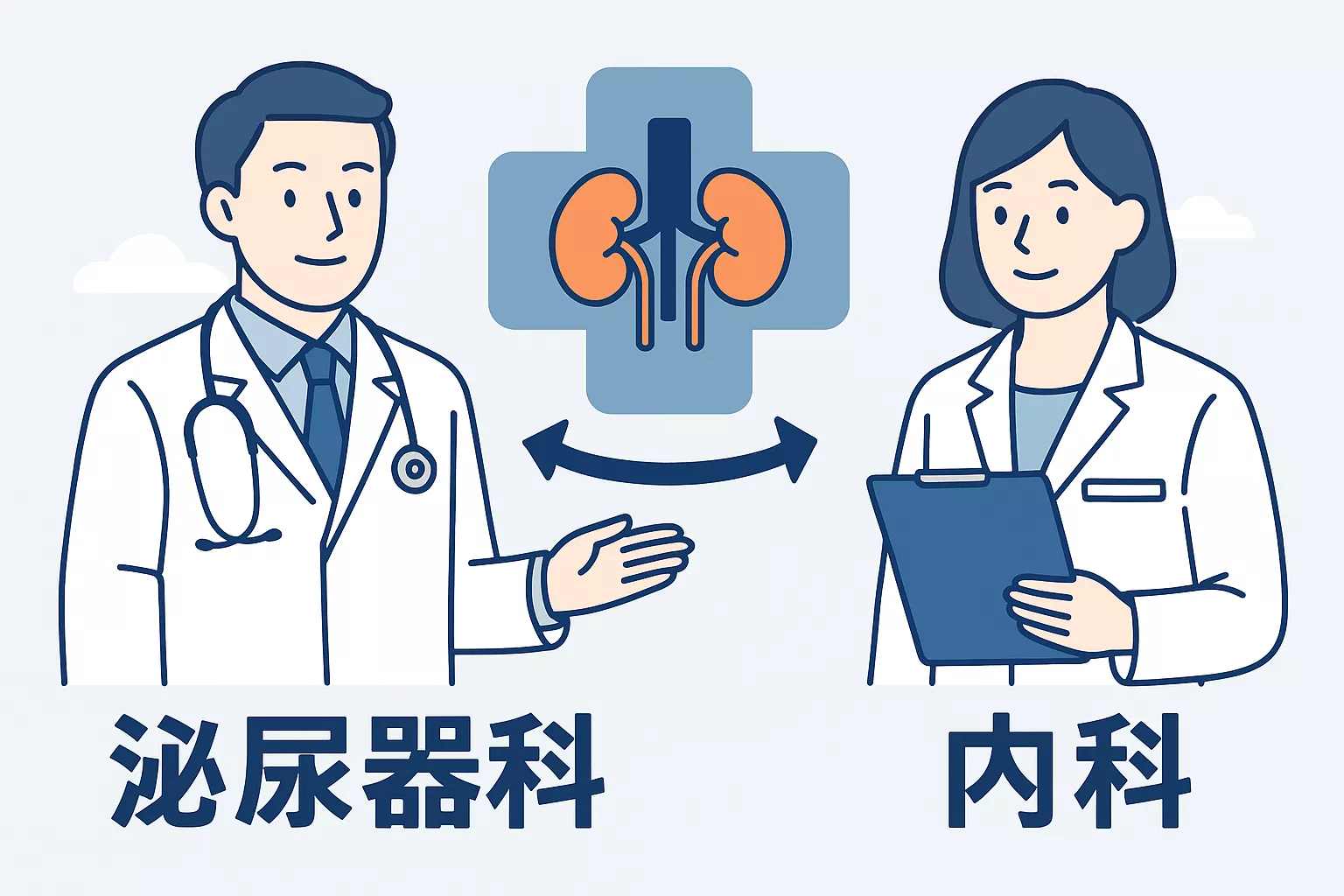
はじめに
高齢化や生活習慣病の増加に伴い、慢性腎臓病(CKD)は地域医療の大きなテーマになっています。腎臓を軸に見ると、泌尿器科と内科は競合ではなく、協働で価値を高め合う関係です。本稿では、内科連携を「診療の質」と「経営の安定」の両面から設計するポイントを整理します。
腎臓を軸とした“協働”の発想
泌尿器科で扱う多くの疾患は腎機能と密接に関係し、内科疾患(高血圧・糖尿病・脂質異常症など)は腎機能低下を進行させます。両者の境界を作るのではなく、共通の目的(腎臓を守る)で診療動線を組むことが、患者にとっても経営にとっても合理的です。
経営面での価値 ― 継続患者と信頼の基盤づくり
- 新規流入の創出: 内科でCKDや蛋白尿を指摘された患者の紹介導線を整え、自然な新患流入を確保。
- 再診率の安定化: BPH・OABなど泌尿器疾患の患者に生活習慣病フォローを併走させ、通院理由を複線化。
- 診療単価の適正化: 尿・血液・エコーの定期検査を仕組み化し、医療の質と収益安定を両立。
- ブランド形成: 「排尿を診る」から「腎臓を守る」へ。地域での差別化に寄与。
実務設計のポイント
1) 定期検査のパッケージ化
- eGFR・Cr・尿蛋白・血圧・体重をワンセットで管理(結果はグラフで見える化)。
- 再診時のルーチン化で説明時間を短縮、納得感を向上。
2) 情報共有の効率化
- 紹介状・返書のテンプレートを整備し、FAX/クラウドでデータ連携。
- 重複検査を避け、患者負担と医療費を抑制。
3) 投薬情報の透明化
- NSAIDs・利尿薬・造影剤など腎機能に影響する薬剤の情報を相互把握。
- 禁忌・用量調整の方針を院内プロトコル化。
4) 生活指導の仕組み化
- 水分摂取・塩分制限・運動の目安をスタッフ/栄養士が説明し、医師の負担を軽減。
- 配布資料と再診時のチェック項目で継続率を維持。
“三方よし+将来よし”で考える
- 患者よし: 複数科を行き来せず、腎・排尿を含めた総合的なケアが身近で完結。
- 医師よし: 専門性を活かしつつ、通院・検査・説明が安定し再診率が向上。
- 地域よし: 透析予防・合併症抑制に寄与し、医療資源の有効活用に貢献。
- 将来よし: 生活習慣病の増加に合わせ、泌尿器科が「腎臓の守り手」として位置づけ強化。
まとめ
泌尿器科と内科の連携は、「患者を取り合う」関係ではなく「共に支える」関係です。腎臓を共通軸に据え、検査・情報共有・生活指導を仕組み化することで、診療の質向上と経営の安定を同時に達成できます。
次回は、「泌尿器科が内科を標榜するという選択」を取り上げ、専門性と経営のバランスをどう取るかを整理します。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。