泌尿器科クリニック経営シリーズ 第6回 泌尿器科が内科を標榜するという選択 ― 専門性と経営のバランスをどう取るか
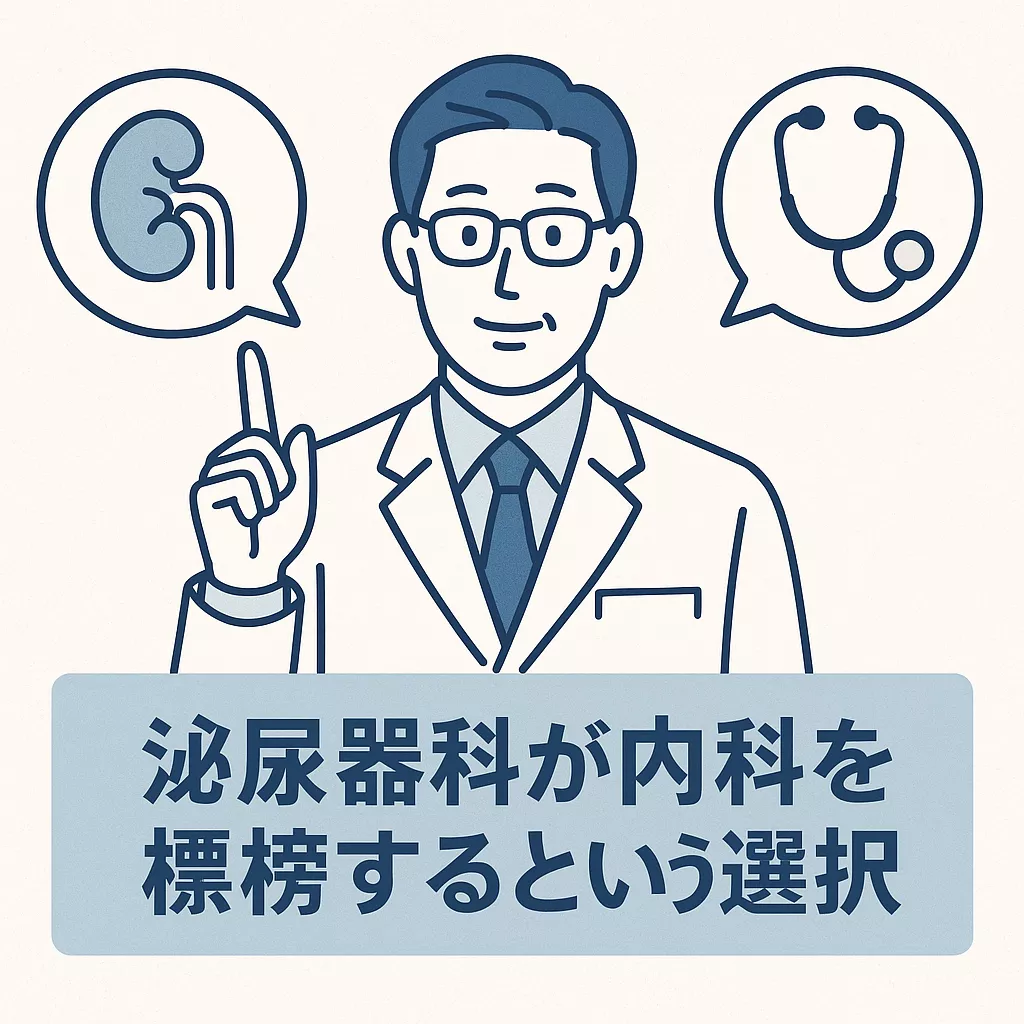
更新日:2025年12月1日
はじめに
泌尿器科クリニックから近年とても多い相談が、「内科を標榜するべきか」というテーマです。 高血圧・糖尿病・脂質異常症といった生活習慣病は腎機能と密接に関わり、患者さんからも「排尿だけでなく腎臓もまとめて診てほしい」という声が増えています(生活習慣病と腎臓の関係については、【生活習慣病と内科クリニック経営①】慢性腎臓病(CKD)と生活習慣病でも整理しています)。
同時に、2026年度診療報酬改定に向けた議論では、「生活習慣病管理」「かかりつけ機能」がより一層重視されています(詳しくは【2026年度診療報酬改定・骨子案】クリニックが今から整えるべき“3つの重点テーマ”もご参照ください)。 この流れの中で、泌尿器科が内科標榜を検討することは、単なる看板変更ではなく、経営構造・診療体制・地域ポジション・スタッフ運用まで含めた「経営判断」になってきています。
本記事は、「泌尿器科クリニック経営シリーズまとめ 治す医療と支える医療をつなぐ“続ける経営”」の第6回にあたります。シリーズ全体の流れを俯瞰したい方は、まずまとめページからご覧いただくのもおすすめです。
ここでは、泌尿器科クリニックが内科標榜を検討する際のポイントを、制度・経営・実務・代替策の順に整理します。
制度的には可能 ― ただし「診療実態」が前提
医師免許は包括的であり、泌尿器科専門医が「内科」を標榜することは制度上問題ありません。 しかし保険診療では実態のある診療が求められるため、以下の準備が欠かせません。
標榜を届け出る前に確認したい3点
- 検査体制: 採血・心電図・血圧測定を無理なく日常運用できるか。
- 人員体制: スタッフが生活習慣病指導・測定補助を担えるか。
- 診療設計: 高血圧や糖尿病を継続管理するフロー(来院頻度・検査項目・説明資料)が設計されているか。
経営面でのメリット
- 患者層の拡大: 「泌尿器+内科」の表示により、高齢層・慢性疾患層の受診ハードルが下がる。
- 診療報酬の多様化: 生活習慣病管理料など点数の幅が広がり、経営が安定しやすい。
- “かかりつけ機能”の確立: 全身管理の安心感が地域での信頼につながり、再診基盤が強化。
注意点とリスク
- 専門性の分散: 泌尿器科の強みがぼやけ、「何でも屋」と見られる可能性。
- 運営コストの増加: 検査設備・試薬・電子カルテ設定・スタッフ教育にコストが生じる。
- 患者ニーズの拡大: 感冒・健診など、本来想定していない相談が増えやすい。
- 診療効率の低下: 専門外相談が多くなると、泌尿器科本来の診療時間が圧迫されることも。
実務的判断のステップ
- 地域分析: 周辺内科の数や距離、競合状況を把握。医師多数地域かどうかは、「医師多数地域での開業戦略」の視点も参考になります。
- 導線設計: 「泌尿器」「腎臓」「生活習慣病」の通院導線を描く。
- 診療範囲の明文化: 例:高血圧・糖尿病に限定し、感冒・健診は受けないなど院内ルールを明確化。
- スタッフ運用: スコア記入、生活指導、検査案内をスタッフが担う体制構築。
- 発信の統一: HP・院内掲示で「泌尿器科+腎・生活習慣病フォロー」を一貫して訴求。
代替戦略 ― 標榜せずに「内科的視点」を持つ方法
標榜しない場合でも、以下の工夫で「腎臓を守る医療」を強化できます。
- 検査設計の拡張: HbA1c・脂質・eGFR・尿蛋白の定期測定と見える化。
- 生活指導の仕組み化: 水分・塩分・運動の目安をスタッフが説明し継続率を向上。
- 伝え方の工夫: Webで「腎臓を守る医療」「血圧・生活習慣病もサポート」を明示。
- 内科との提携: 紹介ルートを院内・HPで明示し、連携の信頼性を可視化。
判断基準の整理
内科標榜を検討する際は、専門性・体制・地域性・ブランディングの4観点を揃えることが重要です。 泌尿器科のコアを守りながら、無理なく生活習慣病をフォローできる体制が整っているか。 地域ネットワークと調和し、院内外の発信が一貫しているか。 これらが満たされるなら、内科標榜は強力な経営施策になり得ます。
まとめ
内科標榜は“やる・やらない”の二択ではありません。 目的を明確にし、導線を設計できるかが成否を分けます。 泌尿器科の専門性を軸に、腎臓・血圧・生活習慣病の管理まで一貫して支援できる体制が整えば、標榜の有無に関わらず地域から選ばれるクリニックに育ちます。
シリーズ全体の流れや、泌尿器科クリニックの“続ける経営”を俯瞰したい方は、泌尿器科クリニック経営シリーズまとめもあわせてご覧ください。
内科標榜を検討されている泌尿器科の院長先生で、「自院ではどこまで診るべきか」「地域の内科との役割分担をどう整理するか」を個別に考えたい場合は、下記の初回整理セッションもご活用ください。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。
考えを整理したい先生へ——声で届ける「経営の迷いを整える」Podcast
日々の診療や経営の中で感じる、「ちょっとした違和感」や「言語化しづらいもやもや」。
そうしたテーマを、私が声で丁寧に紐解いていく番組です。
初回整理セッションの前に、私の考え方や伴走のスタンスを知りたいという先生にもおすすめです。
※外部サービスが開きます