【生活習慣病と内科クリニック経営②】ポリファーマシー対策──薬を「減らす」ではなく「支える」へ
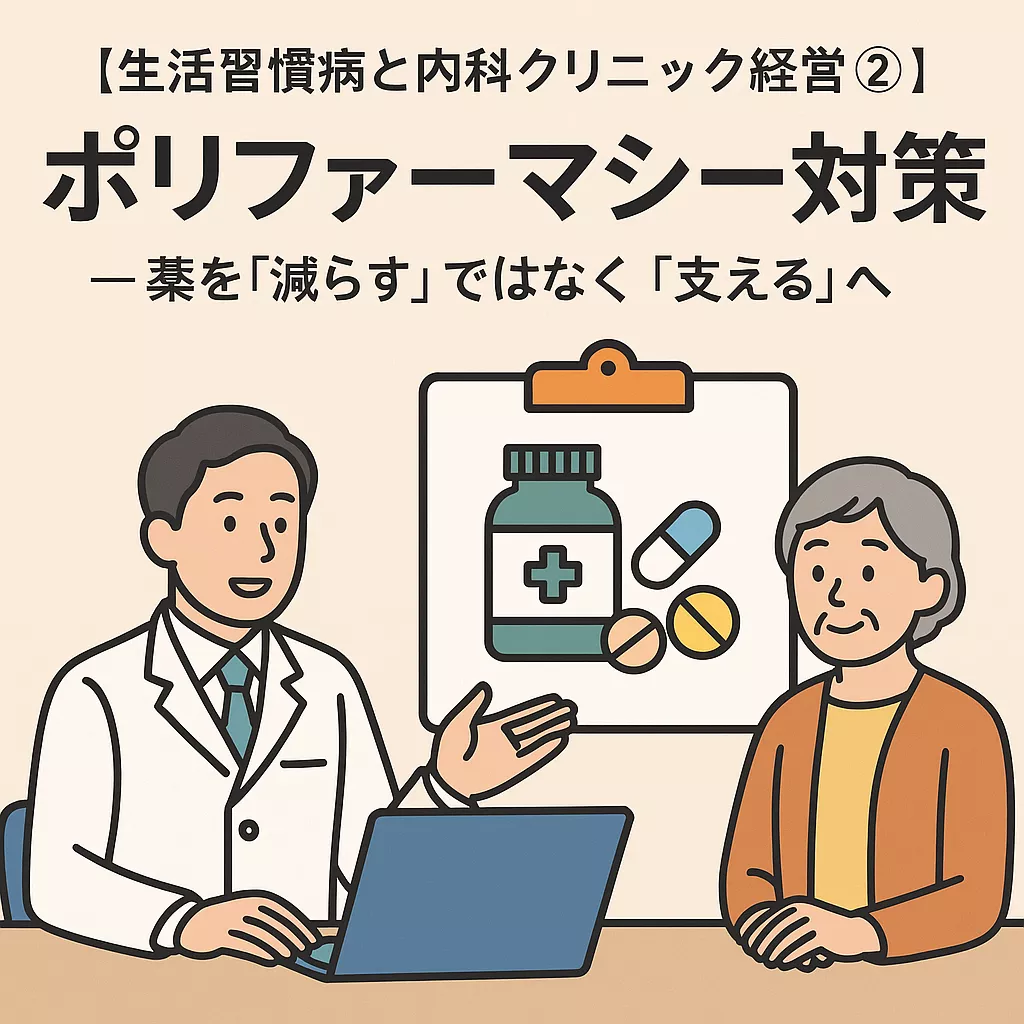
「薬が増え続ける患者に、どこまで介入できるのか」──院長としての悩みはありませんか?
ポリファーマシー(Polypharmacy)は、単に「薬が多い」ことを指す言葉ではありません。
本質は、不必要または有害な薬剤をどれだけ減らせるかにあります。
特に高齢患者では、服薬アドヒアランス低下・副作用リスク・医療費の増大など、経営と医療の両面に影響します。
本記事では、2026年診療報酬改定の流れを踏まえ、内科クリニックが実践すべき「薬剤適正使用」の視点を整理します。
ポリファーマシーとは
一般的には「5種類以上の薬を継続服用」と定義されることが多いですが、重要なのは数ではなく中身の質。
疾患の多様化と高齢化が進むなか、治療の積み重ねが惰性化し、必要性の再確認がなされないまま薬が増える構造が根底にあります。
背景と課題:高齢化社会における構造的リスク
糖尿病・高血圧・脂質異常症・心疾患などの慢性疾患を複数抱える患者は増え続けています。
ガイドライン準拠の治療であっても、薬剤数が増加するのは自然な流れです。
そこに複数診療科からの重複処方や漫然とした継続投与が重なることで、問題が顕在化します。
この状況を整理する力こそが、クリニック経営の信頼性を高める重要な要素です。
2026年診療報酬改定と薬剤適正使用の方向性
過去の改定では「薬剤総合評価調整加算」など、薬剤整理を評価する仕組みが導入されてきました。
次回2026年改定では、多職種連携・服薬情報共有・減薬の成果指標化が議論の中心になる見込みです。
つまり、「薬をどう減らすか」から「どう支えるか」へと視点が変化しています。
薬剤管理体制を整備することは、今後のクリニック経営において避けて通れないテーマです。
クリニックでの実践ポイント
- 処方レビューの定期化: 診療時に薬剤一覧を確認し、不要薬や重複を可視化
- 薬剤師との連携強化: 院外薬局・在宅薬剤管理チームと情報共有し、副作用・残薬をモニタリング
- 患者説明の徹底: 「薬を減らす=治療を止める」ではないことを丁寧に伝える
- チームでの最適化: 看護師・事務・薬剤師が一体となり、慢性疾患管理の中で薬物療法を再設計
薬剤の見直しは、医療安全・経営効率・信頼関係づくりの三要素を同時に高める取り組みです。
患者・地域への周知と連携の形
- 「薬を整理することの意味」を伝える院内掲示・パンフレットの活用
- ホームページやブログで、減薬の考え方を発信(不安の軽減につながる)
- 訪問診療・薬局との連携による継続的フォローアップ
こうした取り組みは「薬を減らす活動」ではなく、患者の生活全体を支える慢性疾患マネジメントの一部です。
地域に開かれた薬剤管理の実践は、今後ますます評価されていくでしょう。
まとめ:薬の“数”ではなく、“納得”を支える経営へ
ポリファーマシー対策の目的は、薬剤数の削減ではなく、必要性とリスクの最適化です。
患者一人ひとりに寄り添いながら、治療方針をチームで見直す姿勢こそが、内科クリニックの信頼を支えます。
「薬を減らす」ではなく、「考えを整理する」──その積み重ねが経営の安定につながります。
シリーズ記事
- 【生活習慣病と内科クリニック経営①】慢性腎臓病(CKD)と生活習慣病 ― 内科クリニックに求められる視点
- 【生活習慣病と内科クリニック経営③】睡眠時無呼吸症候群(SAS)と生活習慣病 ― 内科クリニックでの検査と治療管理
- 【生活習慣病と内科クリニック経営④】フレイルと慢性疾患管理 ― 内科クリニック経営における包括的対応
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分・無料)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。