2026年改定はこう変わる|財務省×厚労省の資料から読む「国民皆保険制度のゆくえ」とクリニックが備えるべき点
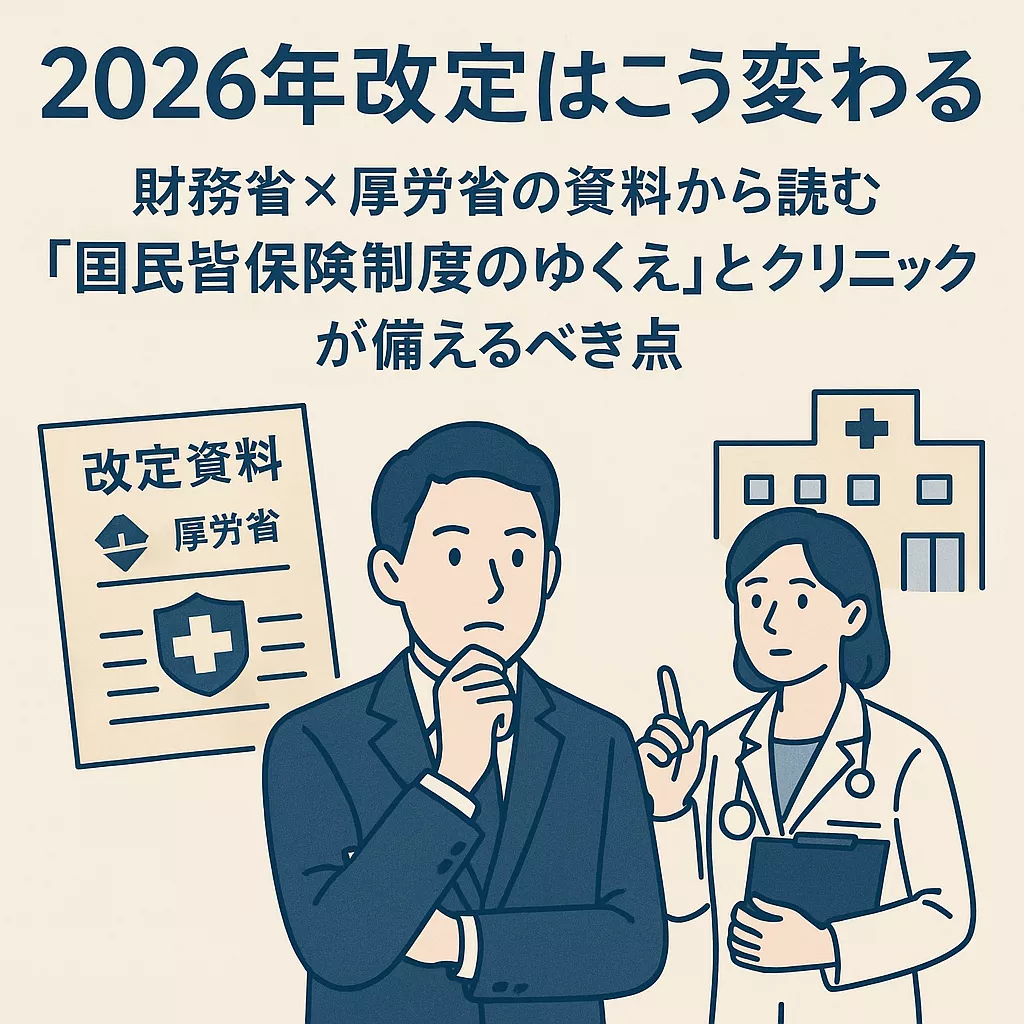
公開日:2025年11月8日(2025年10月・11月時点の情報をもとに作成)
更新日:2025年12月18日
この記事でわかること
- 財務省と厚労省が、2026年診療報酬改定に向けて何を問題視しているのか
- 「国民皆保険制度の持続可能性」が、診療所・クリニック経営にどう影響しうるのか
- 院長・経営者として、今のうちに押さえておきたい“準備の論点”
2026年改定の議論は「点数が上がる/下がる」に目が向きがちです。
ただ、その背後には「国民皆保険制度をどう持たせるか」という、もっと大きな問いがあります。
本記事では、財務省と厚労省が公表する資料を手がかりに、制度の“方向性”を読み解き、クリニック経営に引き寄せて整理します。
はじめに
「国民皆保険制度をどう守るか」。この問いが、いよいよ経営の前提条件になってきました。
「制度の話は正直むずかしい」「細かい資料までは追いきれない」
そんな感覚を持っている院長先生も、少なくないと思います。
ただ、ここで大切なのは、細部を完璧に理解することではありません。
改定がどの方向に向かっているのか、その大枠を押さえておくだけでも、経営判断のブレは大きく減ります。
2025年10月・11月にかけて、財務省・厚生労働省の両省から、2026年度診療報酬改定を見据えた資料が相次いで公表されました。
立場や問題意識は異なりますが、共通するのは──
「限られた資源の中で、持続可能な医療提供体制をどう築くか」という視点です。
ここで重要なのは、「どちらが正しいか」を決めることではありません。
両方の見方を重ねることで、改定の方向性と、クリニックに求められやすい役割が見えてくる、という点です。
2026年診療報酬改定と国民皆保険制度の全体像
2026年診療報酬改定は、単なる2年に一度の調整というよりも、
「皆保険制度を次の10年も維持できるか」を占う局面と捉えたほうが、読み違えが少なくなります。
- 高齢化の進展に伴う医療費の増加圧力
- 物価・人件費上昇による、医療機関のコスト構造の悪化
- 現場の疲弊(採用難・定着難・業務過多)
こうした背景の中で、財務省は「財源・分配・適正化」の観点から、
厚労省は「現場・人材・提供体制」の観点から、それぞれ問題提起を行っています。
改定の方向性をつかむためには、どちらか一方の資料だけを見るのではなく、両者を重ねて読むことが重要です。
診療報酬改定の全体像や「読み解く力」については、次の記事でも整理しています。
▶ 診療報酬改定を“読み解く力”を持つ|2026年に向けて院長が備えるべき経営視点
財務省の視点:「制度を持たせるための引き締め」
財務省の資料では、「制度を持たせる」ために、高コスト構造の是正・生産性改革・給付の適正化といった方向性が強く示されています。
要するに、財務省が最も重視しているのは、「医療費の伸びをどう抑えるか」という点です。
- 診療所・調剤薬局の収益構造に対する適正化の問題意識
- 提供体制の機能分化・連携、再編も含めた効率化
- 医療費抑制に対する強いメッセージ
クリニック経営に引き寄せると、論点は比較的シンプルです。
「地域での役割が説明できる医療」は評価されやすく、
「役割が曖昧に見える医療」は見直しの対象になりやすい。
だからこそ院長としては、まず「自院の収益の前提」を言語化できる状態が土台になります。
- どの診療・どの加算が収益を支えているのか
- その診療は、地域医療提供体制の中でどう位置づけられるのか
- 患者さんにとって、どんな価値を提供しているのか
財務省提言が診療所に及ぼす影響については、次の記事でも掘り下げています。
▶ 🩺財務省提言が診療所にもたらす影響とは――2026年改定に向けて、院長がいま備えるべき3つの行動
厚労省の視点:「人を守るための仕組みづくり」
一方、厚労省の議論は、現場の厳しさを前提に、
「人と体制を守らなければ医療は続かない」という方向に重心があります。
- 物価・人件費上昇への対応
- 医療スタッフの賃上げと処遇改善
- 業務効率化・医療DXの推進
- タスクシフト/タスクシェアの推進
- かかりつけ医機能・地域連携の強化
財務省が「引き締め」で制度を持たせようとするのに対し、
厚労省は「現場を支える仕組み」で持続を図ろうとします。
アプローチは違っても、どちらも「皆保険を続けるための議論」です。
厚労省が示す「治す医療/治し支える医療」の整理は、次の記事でもまとめています。
▶ 改定後に“取り残されるクリニック”にならないために|医師が押さえるべき2026改定の要点 ― 厚労省が目指す「治す/治し支える医療」
3つの視点で整理する「国民皆保険制度のこれから」
ここまでを踏まえると、国民皆保険制度は次の3つの視点で整理すると理解しやすくなります。
- 財源・分配(財務省の視点):限られた財源で、何を優先的に支えるか
- 現場・人材(厚労省の視点):誰が、どんな体制で医療を提供し続けるか
- 意識・文化(現場と社会の視点):私たちは医療をどう使い、どう支えるのか
点数表の細かな改定項目に目を向ける前に、院長としてはまず、
「自院は、この3つのどこに強み・弱みがあるのか」という問いを持つことが、最短の準備になります。
院長・経営者として備えておきたい5つの準備
では、議論が進む中で、診療所・クリニックとして何に備えておくべきでしょうか。
ここでは、無床診療所の院長に押さえていただきたい“準備の論点”を5つに整理します。
すべてを一度に整える必要はありません。
多くの無床診療所では、①業務の可視化と②チーム体制の整理から着手すると、他の論点も見えやすくなります。
- ① 業務の可視化と効率化: ムリ・ムダ・ムラを洗い出し、「紙・二重入力・属人化」を減らす。小さなDXからで十分。
- ② チーム体制の再設計: タスクシフトを前提に、医師・看護師・事務の役割を再整理。「誰が何を担うか」が共有されている状態をつくる。
- ③ コスト構造の点検: 人件費・外注費・固定費を棚卸しし、賃上げ・採用難の中でも「続けられる形」を描く。
- ④ 外来機能と“地域での役割”の整合: かかりつけ機能・専門性・在宅との関係など、自院の立ち位置が説明できるかを見直す。
- ⑤ 患者・家族との対話: 医療の限界や適切な受診行動を共有し、「支える文化」を育てる。慢性疾患の通院の意味づけも含めて丁寧に。
制度を支えるのは、制度そのものではなく現場と地域の関係性です。
改定の方向性を踏まえつつ、「自院として、何を選び、何を手放すのか」を考えることが、これからの数年を乗り切る土台になります。
制度解説やテンプレ導入ではなく、
「その医院の状況・価値観・耐久力」に合わせて整理することを大切にしています。
もし「ひとりでは考えが堂々巡りしてしまう」と感じる場合は、まずは初回整理セッションで、いまの状況と優先順位を整理するところからご一緒できます。
そのうえで、必要に応じて開業・経営(整理)セッションへ進む形です。
まとめ
「国民皆保険制度の持続可能性」は、単に「財政をどう守るか」ではなく、
「地域で医療を提供し続ける関係性をどう続けるか」という問いでもあります。
改定情報に翻弄されるのではなく、「自院として、どんな役割を担い、どんな関係性を築きたいのか」という軸から、制度との向き合い方を整理していく。
それが、結果として“取り残されない”準備につながります。
正解を急がず、
ご自身の「納得解」で進むための時間
開業準備や日々の診療を続けるなかで、「どこか引っかかったまま進んでいる感覚」を抱えていませんか。
初回整理セッションは、結論を急ぐ場ではなく、考えを一度並べ直し、納得して次に進むための対話の時間です。
正解を提示するのではなく、ご自身の判断の軸が見えてくることを大切にしています。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
まずは状況と優先順位を整理し、必要に応じて開業・経営(整理)セッションへ進む形です。
🧩 初回整理セッションを申し込む※売り込みや即決を前提とした場ではありません
迷っている方へ —— Podcastのご案内
日々の診療や経営の中で感じる、言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、
制度や現場の視点も交えながら、声で整理していく番組です。
初回整理セッションの前に、考え方や伴走のスタンスを知りたい先生におすすめです。
※外部サービスが新しいウィンドウで開きます
関連記事
noteでの関連発信
本記事の背景にある「制度を“関係性”で支える」という視点については、noteでも思考のプロセスや現場目線を交えて発信しています。
📝あわせてこちらもご覧ください
“皆保険”を支える関係性──持続可能な医療をめぐる3つの視点(当社作成note記事)