診療報酬改定を“読み解く力”を持つ|2026年に向けて院長が備えるべき経営視点
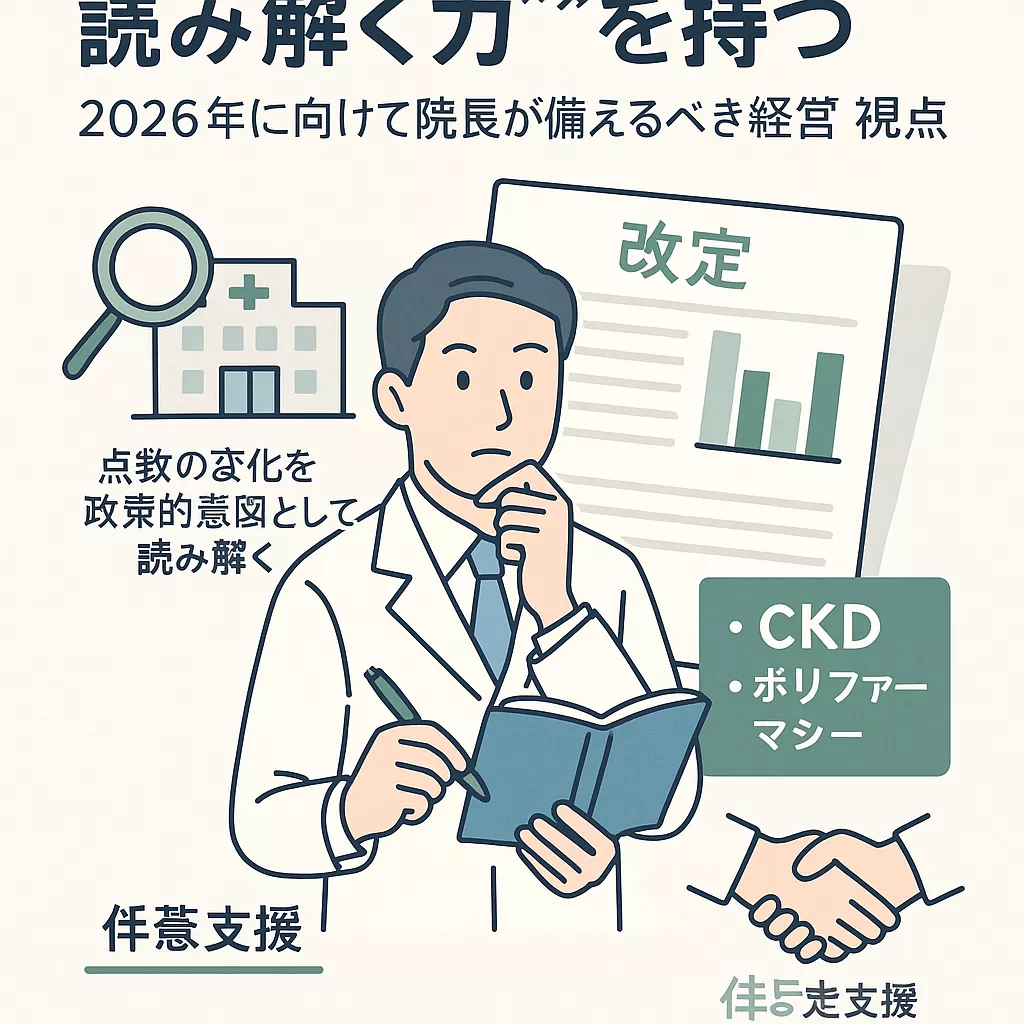
診療報酬改定が話題になると、「点数が上がった・下がった」といった金額面ばかりが注目されがちです。
しかし診療報酬は、単なる収益の増減を示すものではありません。そこには、国が医療機関に担ってほしい役割や、医療提供体制の方向性が明確に反映されています。
つまり、診療報酬の変化は「国からのメッセージ」です。
数字の裏にある政策意図を読み取り、自院の経営判断に活かす視点こそが、これからのクリニック経営に欠かせません。
改定は「何が変わるか」だけを追うと、対応が“作業”で終わりやすくなります。
院長としてどこまで対応し、何を優先するかまで含めて整理すると、判断がぶれにくくなります。
→ 2026年度診療報酬改定を院長の視点で整理した記事はこちら
1. 診療報酬は「政策のサイン」
たとえば新型コロナ禍で新設された「感染症対策実施加算」には、
- 地域で発熱患者を受け入れてください
- 検査・トリアージ体制を整えてください
- 地域医療を守る“砦”になってください
というメッセージが込められていました。
このように、診療報酬は単なる点数表ではなく、「国が医療現場に期待する行動の方向性」を示す政策のサインです。
2. 経営者として読み解く力を持つ
開業医は「医師」であると同時に「経営者」でもあります。
ある加算が強化されたなら「この分野に注力してほしい」というメッセージ。
逆に点数が下がったなら「効率化・統合を促す方向性」と読むべきです。
このように、診療報酬を経営判断の指針として捉えることができるかどうかが、3年後・5年後の立ち位置を大きく左右します。
改定を「やらされる対応」ではなく、自院の役割(提供価値)を更新する機会として扱えるかがポイントです。
3. 「お金の話」を避けない勇気
「お金の話は下品だ」と敬遠されがちですが、診療報酬の理解は利益追求ではなく、医療を持続させるための現実的な言語です。
数字を読めることは、理想を守る力でもあります。
理想と現実をつなぐ“共通言語”として、数字を活用することがこれからの院長に求められます。
4. 2026年改定に向けて注目すべきテーマ
次の改定(2026年)は、超高齢社会への対応が主軸になると考えられます。特に、
- 生活習慣病管理(CKDなど慢性疾患の継続支援)
- ポリファーマシー対策(多剤併用の是正)
- 在宅・外来連携の強化(紹介・逆紹介、地域での役割分担)
- かかりつけ医機能の明確化(相談・継続支援・連携の「見える化」)
- 医療DXの実装(業務効率化と、地域に向けた安心の可視化)
これらは単なる加算対策ではなく、地域で必要とされ続けるクリニックの条件です。
制度の動向を待つのではなく、「国が求める医療をどう自院に実装するか」を早期に考えることが、将来の競争力につながります。
5. 診療報酬改定は「経営の羅針盤」
診療報酬改定は、国が示す医療政策の“道しるべ”です。
開業医にとっては、経営の方向性を見直す絶好のタイミングでもあります。
- 点数の変化を政策意図として読み解く力を養う
- CKD・ポリファーマシー・連携・DXなどを戦略的に導入する
- 数字を「医療を続けるための言語」として扱う
これらを実践できるクリニックこそ、制度改定に左右されずに地域で支持され続ける存在になります。
正解を急がず、
ご自身の「納得解」で進むための時間
開業準備や日々の診療を続けるなかで、「どこか引っかかったまま進んでいる感覚」を抱えていませんか。
初回整理セッションは、結論を急ぐ場ではなく、考えを一度並べ直し、納得して次に進むための対話の時間です。
正解を提示するのではなく、ご自身の判断の軸が見えてくることを大切にしています。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
料金:5,000円(税別)
例えば、こんな場面でご利用いただいています。
- 開業準備や経営判断について、何から整理すべきか分からなくなっている
- 制度や環境の変化を前に、自分なりの考えを一度立ち止まって整理したい
- 一人で考え続けるのではなく、第三者との対話を通じて頭の中を言語化したい
※売り込みや即決を前提とした場ではありません
迷っている方へ —— Podcastのご案内
日々の診療や経営の中で感じる、言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、
制度や現場の視点も交えながら、声で整理していく番組です。
初回整理セッションの前に、考え方や伴走のスタンスを知りたい先生におすすめです。
※外部サービスが新しいウィンドウで開きます