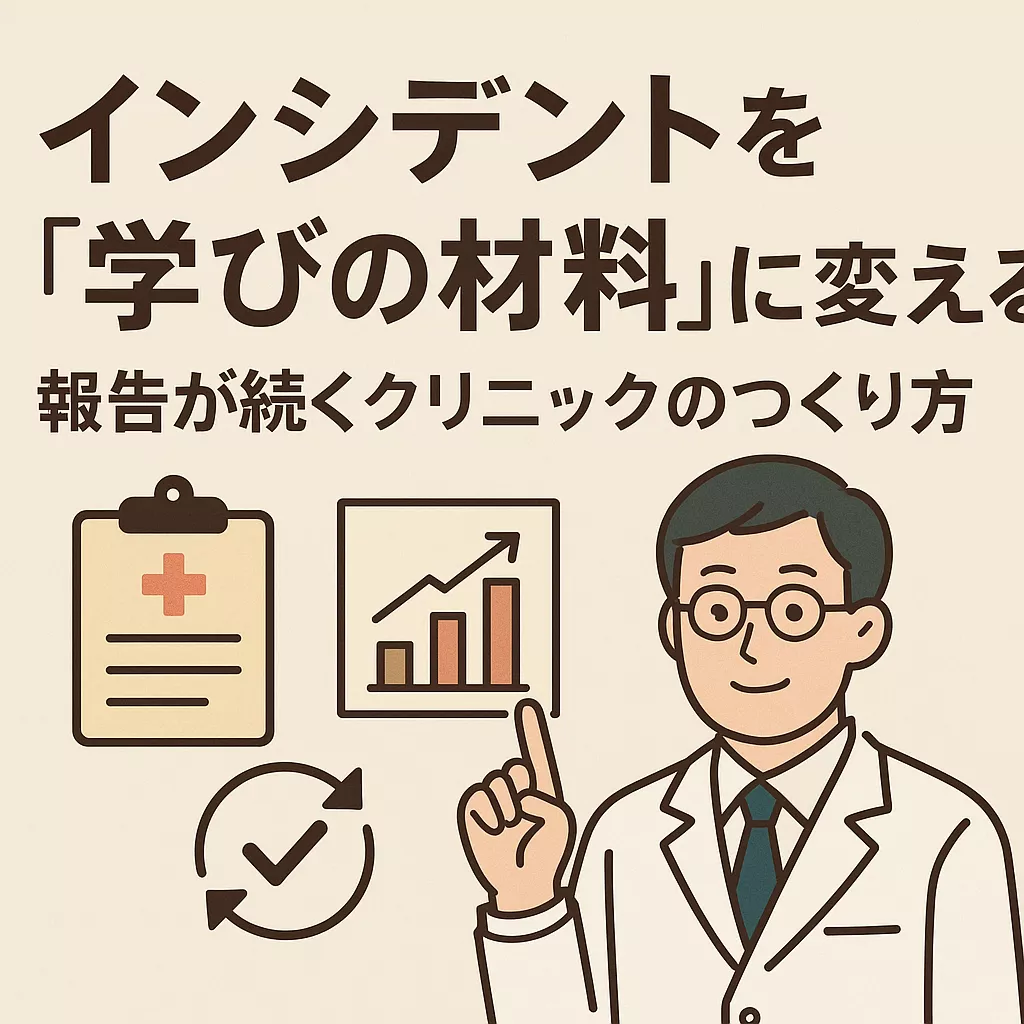ヒヤリ・ハットを「書類」から「学習サイクル」へ。
現場の気づきを“責めず・活かす”文化に変えるのは、院長の意思決定と運用設計です。
まず3つ、当てはまるものはありますか?
- ヒヤリ・ハットの報告がなかなか上がってこない
- 報告書を読んでも、次の改善アクションにつながらない
- レポートが「形式だけ」になっている気がする
一つでも当てはまるなら、インシデントレポートを「経営の道具」として見直すタイミングです。
1. インシデントレポートは“医療安全の文化”を映す鏡
インシデント/アクシデントレポートは、罰則を伴う直接義務ではない一方、 指針や加算の文脈で「収集→分析→改善」の実装が求められます。 小さな「ヒヤリ」を表に出し、組織で学びに変える流れは、患者安全だけでなく スタッフの安心も生みます。
2. 病院の慣行と、クリニック運営の“ギャップ”
病院では安全管理部門や委員会が整い、報告の習慣があります。 一方、小規模クリニックでは様式や運用の未整備が起こりがち。 病院時代の「やらされ感」を引きずると、開業後は文化が根づきにくくなります。
重要なのは、インシデントを経営データとして扱う視点です。 どこにボトルネックがあり、どの工程でエラーが起きやすいかを可視化できます。
3. 院長が押さえるべき3つの基本動作
- 自ら確認し、改善まで責任を持つ:「読んで終わり」にしない(期限と担当者を決める)
- 報告を歓迎する姿勢を明示:心理的安全性を守り、感情ではなく事実と仕組みで向き合う
- 個人ではなく仕組みを直す:再発防止に集中し、工程・役割・環境の改善に落とす
こうした振る舞いが信頼を生み、報告→学習→改善の循環を回します。
4. インシデントを“経営改善の起点”にする手順
件数そのものより、報告から見える業務の詰まりに注目します。
- 処方ミスが散発 → 在庫・ダブルチェックの工程設計+DX(バーコード等)
- 受付・会計のトラブル → 役割分担・導線の再設計、待ち時間の可視化
- クレーム対応の属人化 → 対応マニュアルと記録フォーマットの統一
すべてを一度に直そうとせず、「1つだけ改善」×期限で累積させるのがコツです。
5. 形式で止めない:現場に根づく3つの運用
- 書きやすさ:様式は3項目だけ(状況/対応/学び)。
例)状況:〇月×日 受付で保険証の取り違い/対応:患者へ説明・訂正/学び:本人確認を声掛け+指差しに統一 - 称賛の可視化:月1回の短い共有で「報告ありがとう」を宣言
- アクションの固定:各報告に「1つだけ改善」を必ず紐づける
まとめ:インシデントは“改善の種”
インシデントレポートは書類ではなく経営の鏡です。
院長が改善の起点として向き合えば、クリニックは 「守る組織」から「育つ組織」へ進化します。
インシデント運用が「形だけ」で止まっていると感じたら
ここまで読んで、「考え方としては分かるが、自院の運用設計に落とし込めない」 と感じた院長先生へ。
こうした詰まりは、論点と優先順位の整理でほどけることがあります。
(例:報告様式/共有の場/改善の責任分担/期限の置き方)
事前に「雰囲気」を知りたい方へ
言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、声で整理するPodcastです。
🎧 Spotifyで聴く