神経内科経営シリーズ第1回|神経内科開業の第一歩は「経験の棚卸し」──経営方針はそこから見えてくる
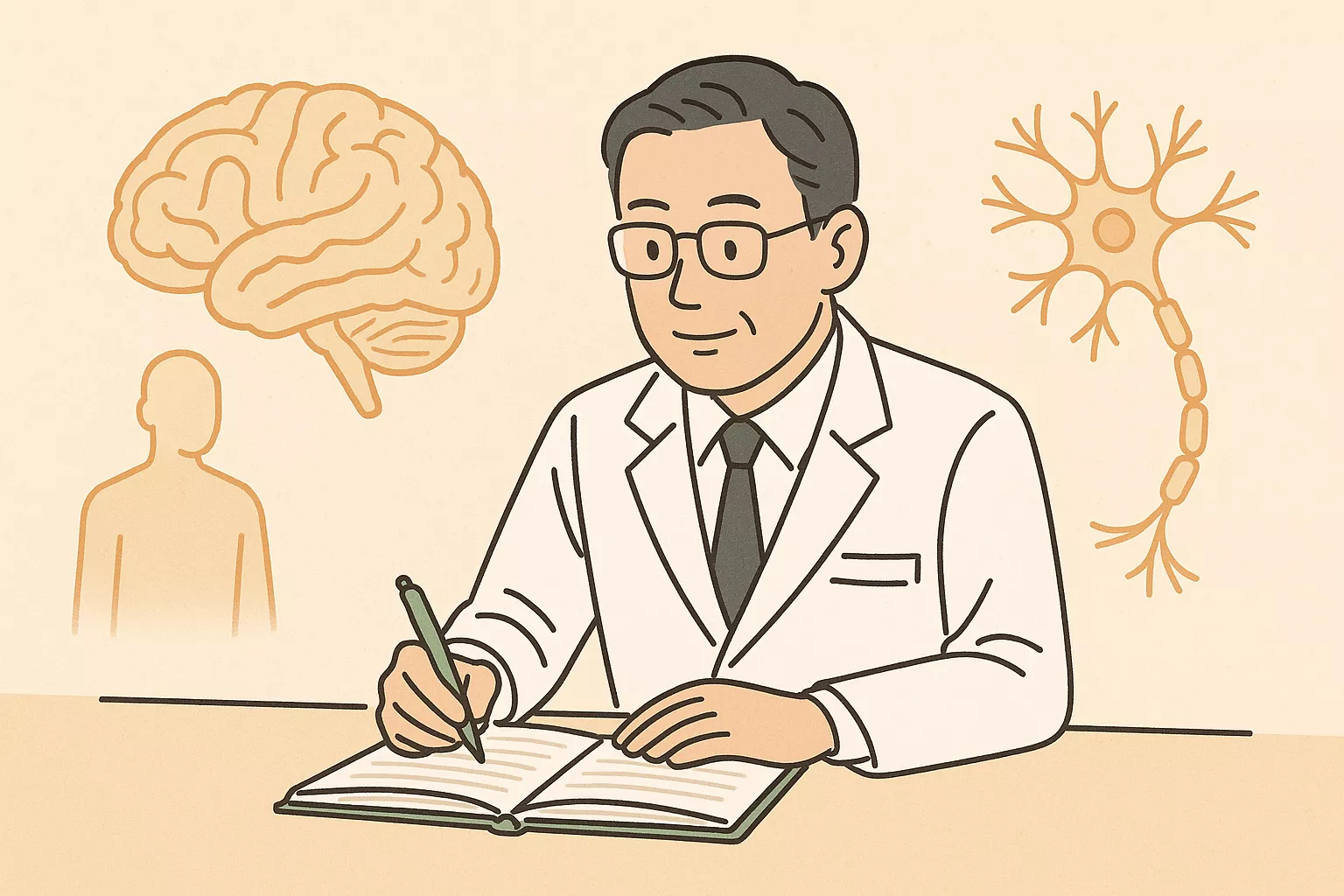
脳卒中、認知症、パーキンソン病、頭痛、てんかん――。神経内科は、扱う疾患の幅が非常に広く、専門性も多岐にわたる診療科です。
そのため、開業を考えるときに最初に立ちはだかるのが「どの領域を柱にするか」という問いです。
すべてを網羅的に扱おうとすると、診療も経営もぼやけてしまいがちです。だからこそ、自分のこれまでの経験を棚卸しし、“どのような医療を続けていきたいのか”を明確にすることが、神経内科開業の第一歩になります。
経験の棚卸しが、経営の出発点になる
神経内科医として歩んできた道のりは、誰一人として同じではありません。
- 急性期病院で脳卒中やてんかんの診療を数多く担当してきた
- 認知症外来でご家族を含めた支援に力を注いできた
- パーキンソン病や片頭痛など、慢性疾患の長期フォローに携わってきた
- 脳卒中後のリハビリや生活機能維持に関わり、再発予防に取り組んできた
これらの経験を整理していくと、「自分が最も手応えを感じてきた診療」や「地域に還元したい専門性」が見えてきます。
それが、開業後の診療方針や経営戦略の土台になります。
「患者さんに届けたい価値」を言葉にする
経験を整理したら、次に大切なのは“どんな価値を地域の患者さんに届けたいか”を言語化することです。
たとえば──
- “もの忘れ”や認知症への不安を、気軽に相談できる場をつくりたい
- 働き世代の頭痛・しびれに専門的に対応し、生活の質を守りたい
- 難病や慢性疾患を抱える方々を、長期的に支える地域の拠点になりたい
- 脳卒中後の患者さんの再発予防・リハビリ支援を続けたい
こうした言葉は、単なる“スローガン”ではなく、診療方針や情報発信、チームづくりの指針にもなります。
「自分はどんな医療を届けたいのか」という想いを明確にすることが、ブランディングの第一歩です。
地域との関係性を描く
神経内科は、内科・脳外科・整形外科・リハビリ科など、周囲との連携が欠かせない診療科です。
開業前から「地域の中でどんな役割を担うか」を描いておくと、診療の立ち上げがスムーズになります。
- 急性期の対応は大病院に任せ、慢性期・生活期を支える立ち位置を明確にする
- 「頭痛・しびれ外来」「認知症相談」など、地域住民との接点を設計する
- リハビリや生活支援を通じて、患者さんの再発防止とQOL向上に寄与する
- 介護・在宅医療との連携を視野に入れ、地域包括ケアの一翼を担う
自院の立ち位置を意識することで、紹介・逆紹介の流れが自然に生まれ、地域全体で患者さんを支えるネットワークが築かれていきます。
まとめ|“広さ”ではなく、“深さ”で勝負する
神経内科開業においては、すべての疾患をカバーしようとするよりも、自分が積み重ねてきた経験から生まれる“深さ”に焦点を当てることが重要です。
経験の棚卸しと、患者さんに届けたい価値の言語化。
この2つを丁寧に行うことで、開業後もぶれない診療方針と、地域に伝わるメッセージが育っていきます。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。