泌尿器科クリニック経営シリーズ 第2回 急性期対応は“知ってもらう入り口”
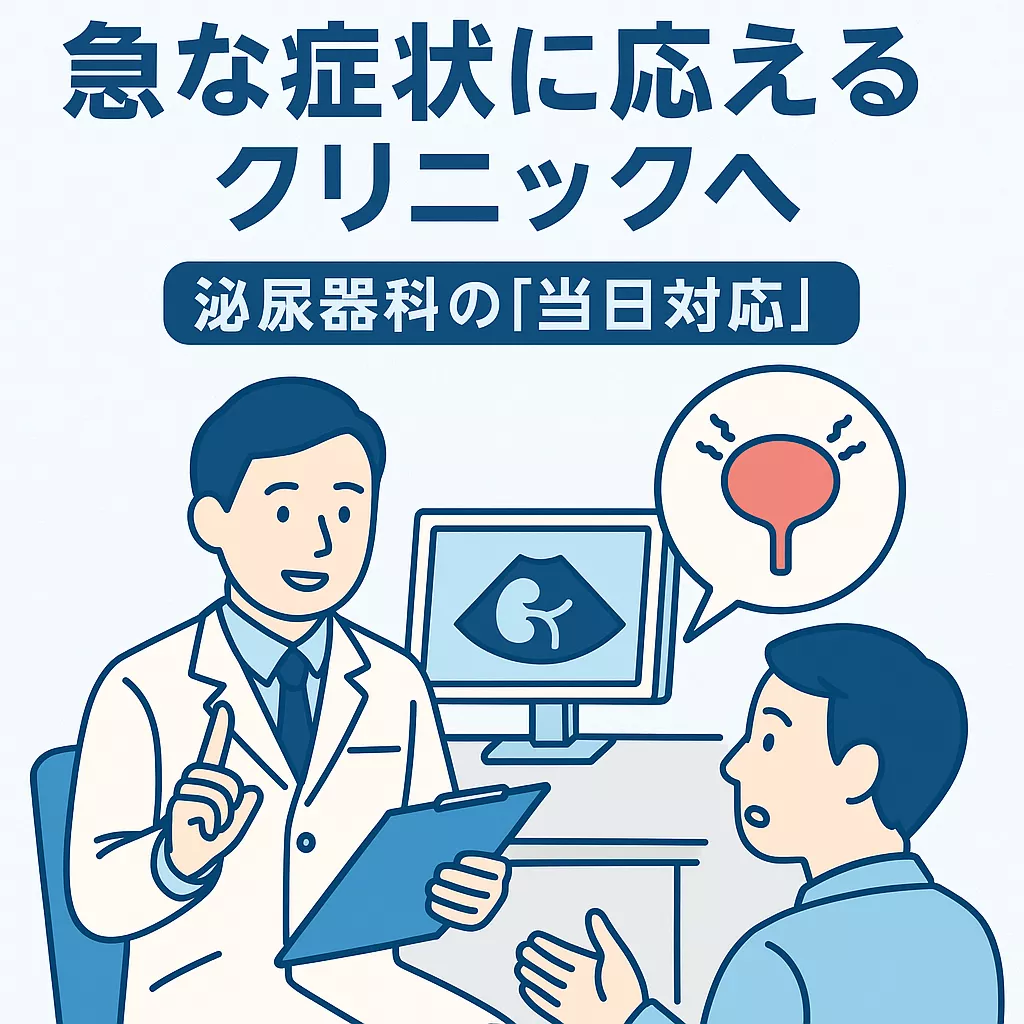
はじめに
泌尿器科クリニックの経営において、急性期対応は「知ってもらう入り口」かつ「収益の入口」です。尿路結石の激しい痛み、膀胱炎による排尿痛、突然の血尿――いずれも患者さんの「今すぐどうにかしてほしい」という強い受診動機につながります。
この場面で的確に応えることは、症状の改善に留まらず、地域で「ここなら安心できる」という認知を高め、結果として経営の安定に直結します。
新規来院のきっかけと経営的意味
- 急性症状:結石疝痛、膀胱炎/腎盂腎炎の発熱、急性尿閉、血尿など。
👉 これらは「当日受診」が前提となるため、新規患者との接点を得る上で極めて重要な機会となります。
※ 膀胱炎は女性患者に多く、「恥ずかしい」「待合で居心地が悪い」と感じながら受診されることがあります。心理的ハードルを下げる工夫は継続通院に直結します(詳しくは 第7回「患者心理とブランディング」)。 - 健診異常:PSA高値、eGFR低下、尿潜血など。
👉 受診時に検査計画と再診日を即時提示することで、再診率の確保=継続収益の起点になります。 - デリケートな相談:ED・性感染症・不妊など。
👉 プライバシー配慮の有無が評判/口コミ形成に大きく影響します。
急性期診療を“経営資産”に変えるフロー
受付〜トリアージ(最初の5分)
- 症状・発熱・血尿・痛みスコアの確認 → 検尿先行+バイタルで即分岐。
- 結石疑いは鎮痛先行、感染徴候には迅速検査・処置で不安を早期に低減。
当日にできる検査・処置(最小装備)
- 尿定性/沈渣、腎膀胱エコー、(可能なら)尿流量測定
- 導尿/留置、座薬・点滴の最小在庫
- 経営実務: 尿検査やエコーは診療報酬の積み上げが効き、単価の安定化に寄与。
その日の出口設計(会計前に完了)
- 処方+セルフケア指導(飲水・安静の目安・注意点)
- 48〜72時間以内の再診予約を確定(受付で確実に押さえる)
- 悪化時の連絡先を明示、説明紙(A5)を手渡し/QRで予約変更可
再診につなげる言葉かけ
「今日は痛みを取ることを第一にしました。3日後にもう一度確認させてください。良くなっているか、一緒に見ましょう。」
「検査結果と注意点はこの紙にまとめました。QRから予約変更もできますので、安心して次回もいらしてください。」
経営実務: こうした一言と書面化は、患者の安心=自然な再診率向上につながり、継続外来の基盤になります。
経営指標としての急性期対応
- 新規患者比率: 急性期でどれだけ新規を取り込めているか
- 再診率: 急性期→慢性期フォローへ移行できている割合
- 検査実施率: 尿検査・エコー施行率=診療単価の安定性
これらを定期レビューすることで、「診療フローの改善」=「経営改善」に直結します。
まとめ
急性期対応は、患者さんにとっての救いであると同時に、クリニックにとって「知ってもらう入り口」であり「収益の入口」です。症状改善で信頼を得つつ、検査・処置・再診予約までを一気通貫で設計することで、経営の安定基盤を築けます。
次回は、慢性期診療を「支える医療」として、どのように経営資産へ転換していくかを取り上げます。
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。