院長が成果を出すために見直すべき“考え方”とは ― 「方法」より先に「問題」を見極める力
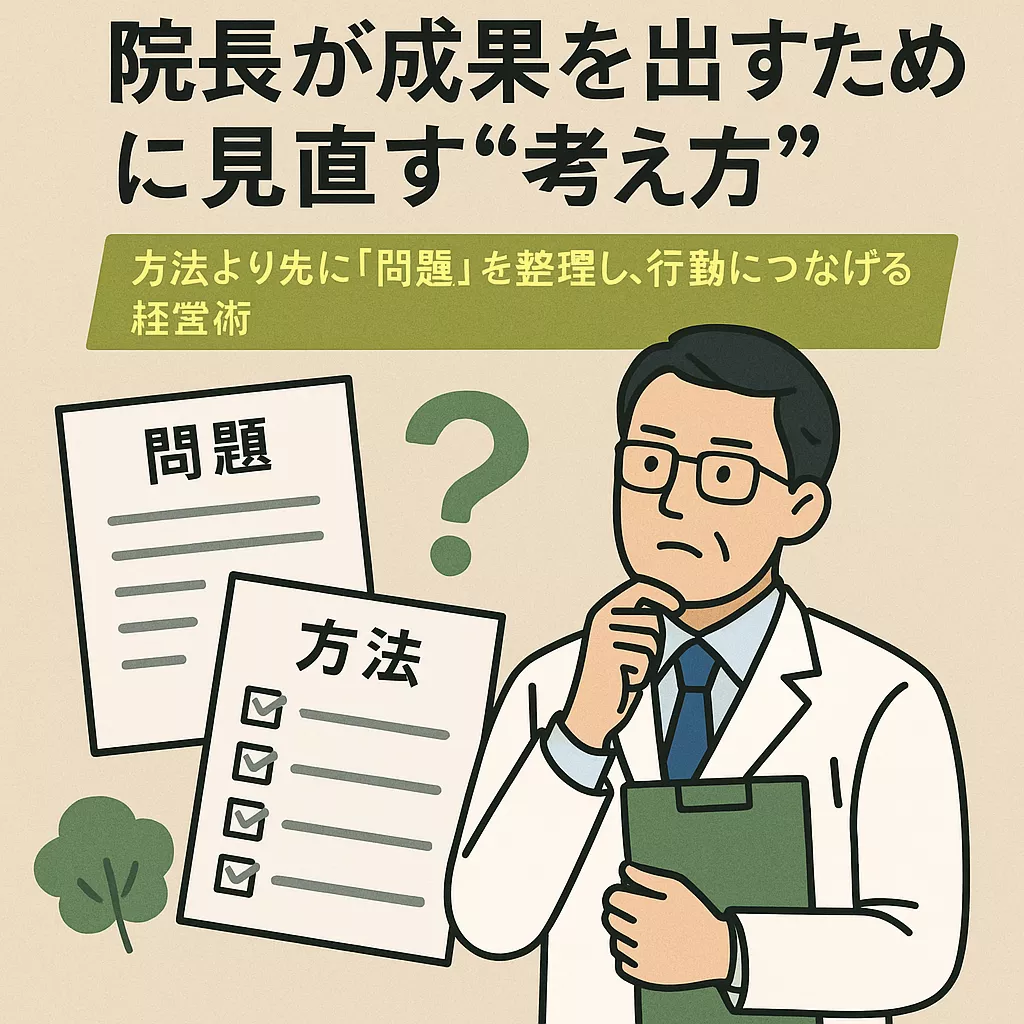
「まず方法を教えてほしい」というご相談は多く寄せられます。
ですが、本当に成果を出すクリニックほど、“何の問題を解くのか”を先に定義しています。
方法はあくまで手段であり、順番を間違えると成果は長続きしません。
まず、次の3つのうちいくつ当てはまりますか?
- 新しいツールを導入しても、思ったほど成果が出ていない
- 問題を整理する前に「何を導入するか」ばかり考えてしまう
- 職員や外部業者との打ち合わせが、いつも“手段の話”で終わる
ひとつでも当てはまる場合、今の経営は「方法先行型」に偏っているかもしれません。
短期的に成果を出す「方法先行型」
方法先行型は、行動が速く結果が見えやすいという強みがあります。
たとえば予約システムを導入して電話対応が減る、Web問診を導入して来院率が上がる、 診療報酬の加算を取得して収益が伸びる――このような変化はわかりやすく、現場のモチベーションにもつながります。
しかし、方法はあくまで「手段」です。課題が整理されていないまま導入すると、 「導入したけれど定着しない」「思ったほど効果が出ない」という結果にもつながりかねません。
長期的に成果を出す「問題先行型」
一方で、「そもそも何が問題か」を掘り下げる姿勢は地味に見えますが、長期的な成果を生み出します。
たとえば新患が減っている場合――
- 原因は「宣伝不足」なのか、「導線設計の不備」なのか
- あるいは「地域の人口構造の変化」なのか
また、スタッフの定着が悪い場合も、給与ではなく 「人間関係」「評価」「役割の不明確さ」に根本的な理由があることが少なくありません。
本質を見極めるには時間がかかりますが、 一度そこに辿りつけば施策の精度と持続性が格段に上がります。
成果を出すクリニックの共通点
成果を出しているクリニックは、「問題」と「方法」を行き来する思考を持っています。
まず問題を整理し、優先順位を決め、その上で最も効果的な方法を選び、 実践と改善を繰り返します。このプロセスを持つことで、
診療報酬改定や地域人口の変化などの外部要因にも、柔軟に対応できます。
伴走型支援の役割
私が「伴走型支援」と呼んでいるのは、単に方法を伝えることではなく、 問題の構造を一緒に見立てるプロセスです。
やり方だけを教えるのは簡単ですが、それでは一時的な成果で終わることもあります。
「なぜその方法が必要なのか」を院長先生と共に整理し、自院の現場に合った形へ落とし込むこと。
それが、私の支援の原点であり、持続可能な経営につながる第一歩です。
まとめ
- 短期的に動くのは「方法先行型」
- 長期的に成果が続くのは「問題先行型」
- 成果を出すのは、「問題」と「方法」を行き来できる経営者
「何を導入するか」よりも、「なぜ必要なのか」を整理することが、
院長先生の意思決定を強くし、組織の自走力を高めます。
関連記事
頭の中の“もやもや”を整理し、次の一歩を見つけたいときに
日々の診療や業務のなかで、「言葉にしづらい違和感」を抱える院長先生は少なくありません。
初回整理セッションでは、経営の前提となる“考え”を丁寧に言語化し、納得感のある方向性を一緒に見つけていきます。
即答よりも、「腑に落ちる」時間を大切にしています。まずは話すことから、整理がはじまります。
🗣️ 初回整理セッション(60分)
経営方針・組織づくり・診療体制・情報発信・人との関わり方など、幅広いテーマに対応。
“考えの整理”を通じて、先生の中にある答えを見つけていきます。