小児科経営シリーズ①|小児科クリニック経営のこれから――制度変化から読み解く“治す×支える”医療
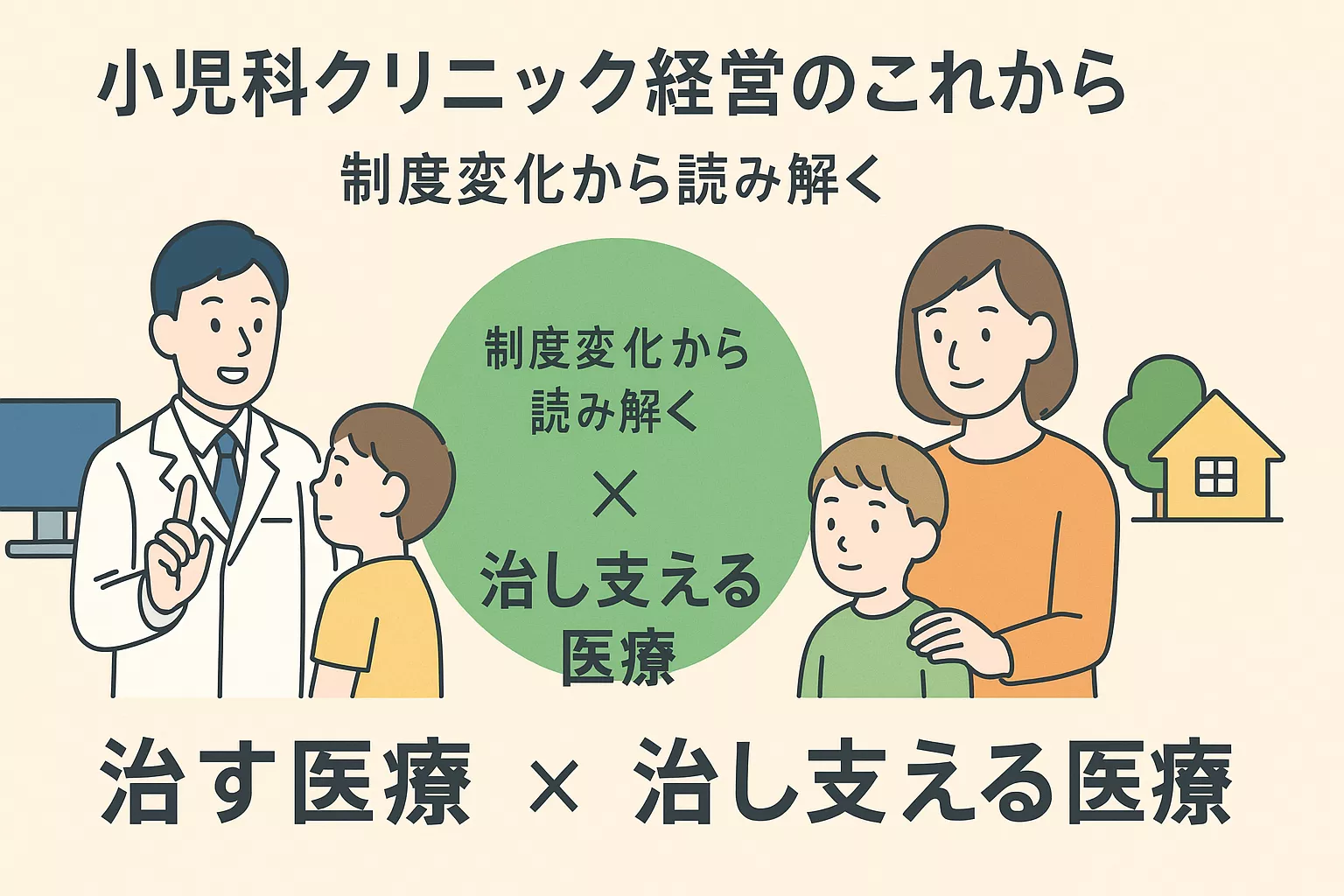
小児科クリニックは、急性疾患を「治す」場であると同時に、家族の不安や日常を「支える」場でもあります。 少子化・慢性疾患・共働きの増加、そして制度改定や医療DXの推進を踏まえると、 経営は“治す×治し支える”を両輪に再設計する段階にあります。 本稿はシリーズ総論として、①制度の方向性 → ②将来の経営設計 → ③施設・サービスへの落とし込みの順に整理します。
小児科は、医療制度の中でも社会的役割が比較的明確で、構造そのものが大きく揺らぎにくい診療科です。 他診療科(皮膚科や生活習慣病中心の内科、心療内科など)と並べて見たときも、地域における必要性や公共性が意識されやすい位置づけにあります。
一方で、経営の現場に目を向けると、重心が少しずつ移動してきています。OTC化や受診控えの影響に加え、人件費上昇・スタッフ確保の難しさが重なり、 「患者数が多いかどうか」だけでは語れない局面が増えました。 これからは、季節波動を前提にした固定費の考え方や、相談・説明・予防をどこに位置づけるかといった“設計の巧拙”が、静かに差として表れやすくなります。
制度の方向性を“経営判断”に翻訳する
- “治す”と“治し支える”の両立:急性期対応に加え、喘息・アトピー・食物アレルギー、発達や不登校への支援など、生活と学びに寄り添うケアが重視される。
- 医療DXの推進:オンライン資格確認、標準化された情報連携、医療DX推進体制の整備など、ICT活用を前提にした評価と運用が求められる。
- 地域包括的な支援:医療機関単体ではなく、家庭・学校・保育・行政が関わる「地域のチーム」で支える流れが加速。
これらは単なる“要件”ではなく、経営の前提です。小児科クリニックには、「早く治す」だけでなく、 家族を継続的に支える仕組みの構築が求められます。 関連:小児科=まちの保健室
将来の経営設計:役割・連携・指標・収益の設計図
1) 役割の再定義 ― “最初の相談窓口(ハブ)”へ
- 急性期:発熱・感染症・胃腸炎などの初期対応
- 慢性・発達:喘息・アトピー・食物アレルギー、睡眠・不登校などへの継続支援
- 家族支援:育児不安、就労中の保護者支援、学校・保育園との橋渡し
2) 他診療科との連携(例)
- 耳鼻科:中耳炎・副鼻腔炎の治療と、言語・発達への影響を踏まえた共同フォロー
- 皮膚科:アトピー性皮膚炎や難治性湿疹の継続ケアとスキンケア指導の共通化
- 心療内科:不登校・睡眠障害など心身の課題への専門治療と日常フォロー
- 呼吸器内科:重症喘息や思春期以降の移行期ケア(成人領域への橋渡し)
3) 日々見るべき経営指標(意思決定のためのKPI)
- 継続フォロー率:慢性・発達支援の継続がどれだけ保てているか
- 予防の受け忘れ率:ワクチン・健診が期限内に実施できているか
- 紹介・逆紹介の滞留:連携先で詰まっていないか/フィードバックは戻るか
- 保護者の安心度:説明の伝わり方(アンケート・口頭確認・口コミ)
- スタッフ育成度:説明・指導の標準化と属人化の抑制状況
4) 収益バランスとリスク分散
季節変動や流行依存を軽減するため、急性 × 慢性 × 予防 × 相談のバランスを設計。 あわせて、波がある前提で固定費(特に人件費)の置き方を見直し、運用で吸収できる余白を確保します。
- 予防:ワクチン・健診を計画的に推進(来院動機の安定化)
- 慢性・発達支援:プログラム化し継続率と品質を高める
- 相談・教育:学校・保育連携相談、保護者教室など“支える”サービスを設計
施設・サービスへの落とし込み(明日からできる実装)
- Web予約・事前Web問診:受診理由・重症度・感染疑いで仕分けし、適切な枠と動線へ
- AI電話・自動応答:FAQ・予約変更の自動化で電話混雑を緩和
- 院内動線:発熱・感染疑いと一般外来の動線分離、安心できる待合設計
- オンライン診療・情報共有:慢性疾患や保護者相談を継続的に支援
- データの見える化:成長曲線や治療計画の共有(患者ポータル等)
- 地域との橋渡し:学校・保育・行政・地域資源との連携を“手順化”
今日の問い
1) 自院の価値観を一言で表すと?(“治す×治し支える”のバランス)
2) 来季の優先テーマはどれか?(急性/慢性・発達/予防/相談)
3) 明日から変えられる運用は?(予約・問診・動線・説明・連携)
正解を急がず、
ご自身の「納得解」で進むための整理の時間
開業準備や日々の経営のなかで、
「考えているはずなのに、なぜか前に進めない」
そんな感覚を抱えることは珍しくありません。
初回整理セッションは、答えを出す場ではなく、
いま頭の中にある論点や引っかかりを、一度言葉にして整えるための時間です。
🗂 初回整理セッション
料金:5,000円(税別)
最初に30分だけZoomで顔合わせを行い、
その後14日間、Chatworkまたはメールで整理を進めます。
例えば、こんな状態でご利用いただいています。
- 開業や経営について、何から整理すればいいのか分からなくなっている
- 制度や環境の変化を前に、自分なりの判断軸を一度立ち止まって整えたい
- 決断の前に、考えを言葉にして確認する時間がほしい
※この時点で何かを決める必要はありません。
売り込みや契約を前提とした場ではありません。
※整理を進めた結果、必要だと感じた場合のみ、
月額の伴走(開業・経営整理セッション)を選ぶこともできます: 詳細
事前に「雰囲気」を知りたい方へ
日々の診療や経営の中で生まれる、
言葉にしづらい違和感や判断の迷いを、声で整理していくPodcastです。
初回整理セッションの前に、
考え方や伴走のスタンスが合いそうかを確かめる入口としてご利用ください。
※外部サービスが新しいウィンドウで開きます